特定技能1号、6月末で33.3万人 ベトナムが14.8万人で最多
法務省・出入国在留管理庁は2025年6月末時点の特定技能在留外国人数を公表。総数は33万6,196人(速報)、うち特定技能1号が33万3,123人、2号が3,073人。国籍別ではベトナムが14万8,486人で最多となった。
一次資料:入管庁「特定技能制度運用状況(令和7年6月末)」、主要報道:VIETJO(2025/10/06配信)ほか。
目次
ポイント
- 特定技能在留者:336,196人(過去最多を更新)
- 内訳:1号 333,123人/2号 3,073人
- 1号の国籍:ベトナム 148,486人(約44.6%)、インドネシア 約69,700人(約20.9%)、ミャンマー 約35,300人(約10.6%)、フィリピン 約32,600人(約9.8%)、中国 約20,200人(約6.1%)
簡易表:特定技能1号 上位国(2025年6月末)
| 順位 | 国・地域 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナム | 148,486 | 44.6% |
| 2 | インドネシア | 約69,700 | 20.9% |
| 3 | ミャンマー | 約35,300 | 10.6% |
| 4 | フィリピン | 約32,600 | 9.8% |
| 5 | 中国 | 約20,200 | 6.1% |
現場への示唆
- 受け入れの偏在:ベトナムへの集中が続く。供給国の多様化と、分野ごとの需給見直しが中長期の安定に不可欠。
- 地域の支え:日本語教育、住居、交通安全、医療・労災など自治体負担の「見える化」と費用対効果の検証が必要。
- 2号の活用:2号(熟練層)はまだ小さいが、定着・熟練化が進むと企業側の再教育コスト低減に資する。
制度の位置づけ
特定技能は人手不足分野での即戦力受け入れを想定。1号は在留期間通算5年・家族帯同原則不可、2号は熟練で更新上限なし・家族帯同可(詳細は告示・運用要領を参照)。
編集部クロ助とナルカの視点から
 編集長クロ助
編集長クロ助受け入れが進むほど、言語・住宅・保険など“持続性コスト”を同時に管理する必要があるにゃ。統計は伸びても、現場の吸収力を測る指標がまだ弱いにゃ。



一方で、求人が埋まって経済が回るのは事実。特に地方の製造や食品分野では助かってる声が多いよ。



だからこそ、供給国の偏在リスクを減らしつつ、2号への移行や技能の見える化で“長期の質”を上げるのが国益に合うと思うにゃ。
一次資料・主要報道
編集デスクまとめ
- ファクト:6月末の特定技能は33.6万人、1号33.3万人・2号3,073人。国籍はベトナムの比重が約45%。
- リスク:供給国・分野の偏在、地域の教育・住居・保険等の受け皿のボトルネック。
自治体単位で「受け入れ許容量(言語教育席数・住宅在庫・相談窓口稼働)」のKPIを公開し、国の支援配分に反映が必要。
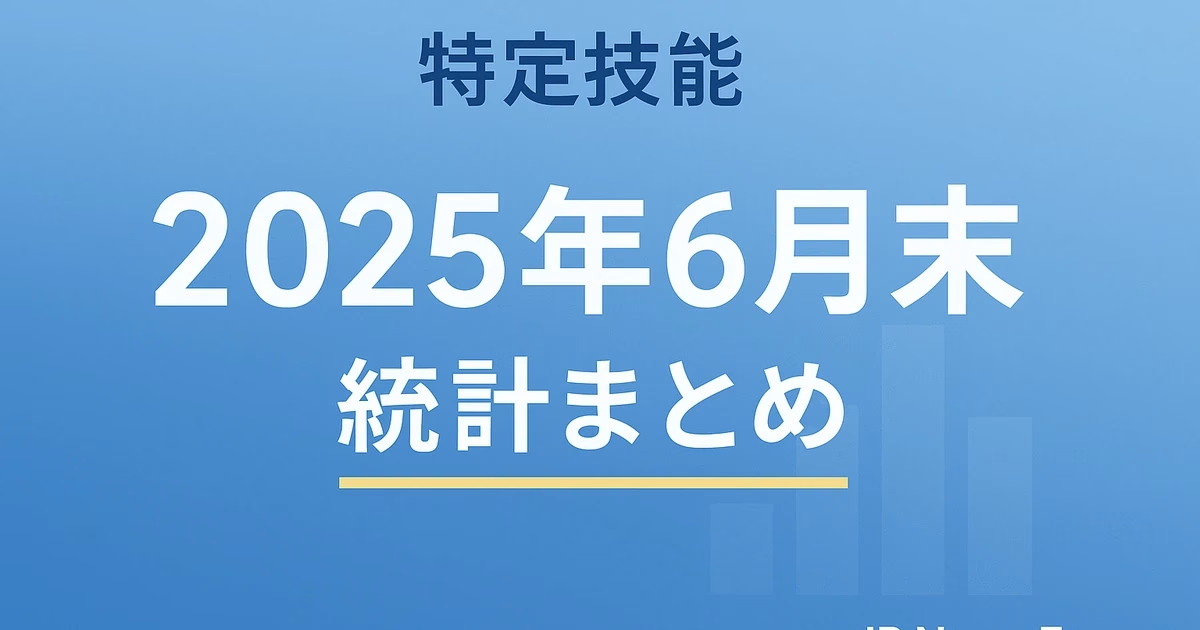



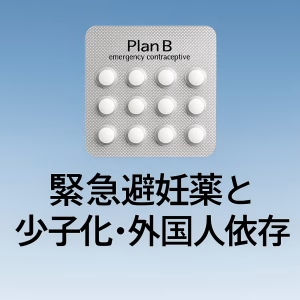
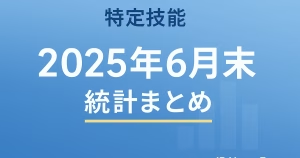
コメント