公開日:2025年8月27日 最終更新日:2025年9月10日
新潟県三条市とJICA(国際協力機構)、慶應義塾大学SFC研究所が2024年7月26日に締結した「地域おこしと国際協力に関する連携協定」が注目を集めています。目的は人材育成や地域活性化ですが、協定文にある「定住促進」という表現がSNSで「実質移民政策ではないか」と議論を呼びました。外務省やJICAは「移民政策とは無関係」と否定しています。本稿では協定の背景と目的、誤解の要因、地域や国への影響を整理します。
JICA:新潟県三条市・慶応義塾大学SFC研究所・JICAによる 「地域おこしと国際協力の研究開発と推進に関する連携協定」について
内部リンク:JICAとは 活動を解説 国際協力と日本社会への影響
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ





協定の背景と内容
三条市は人口減少と若者流出に直面しており、地域おこし協力隊などを活用した地域振興に取り組んできました。今回の連携協定では、地域課題解決と国際協力を組み合わせ、研修・人材育成・交流事業を進めることが柱とされています。
具体的には、国際研修の受け入れや地域人材の育成、地域課題解決のための研究開発を実施する予定です。JICAは協力人材を派遣し、慶應SFC研究所は教育・研究を支援する形で関与します。
三条市|JICA・慶應SFCと連携協定(2024年7月26日)
JICA|プレスリリース(2024年7月26日)
誤解の要因と波紋
協定文には「定住促進」という表現が盛り込まれていました。この言葉が「外国人の永住促進」を連想させ、「移民政策の一環ではないか」との誤解を招きました。SNSでは「実質移民政策では?」という批判が拡散しましたが、JICAや三条市は「定住促進=地域に根差した人材育成を指すもので、在留資格制度とは無関係」と説明しています。
三条市:三条市の国際交流に関する報道に関しまして
内部リンク:JICAと技能実習・特定技能制度 役割と日本社会への影響を解説
地域住民の声
地元の住民からは「人口減少対策として期待したい」との声がある一方、「実際に外国人が定住することになれば地域コミュニティに影響が出るのでは」との不安も聞かれます。商工会関係者からは「労働力不足の解消につながるなら歓迎」との意見もあり、賛否が分かれています。
Yahooニュース:三条市が「外国人移住を促進」…誤情報をJICA否定、市も「冷静に」 「ホームタウン」問題、地域おこし関連協定に飛び火






国内比較と海外事例
日本国内では、技能実習や特定技能制度が「実質移民」と批判されてきた経緯があります。今回の協定も同様に誤解されるリスクがあります。
欧州では地方都市の研修プログラムが「移民受け入れ」と報じられ、治安や統合問題に発展した事例もあります。国際協力を発信する際の表現には慎重さが求められます。
統計データで見る現状
・在留外国人数(総数):約320万人(2024年末、出入国在留管理庁)
・ナイジェリア人:約3,500人(2024年末、同上)
・技能実習生:約35万人(2023年末、厚労省)
・特定技能2号取得者:約2万人(2024年、入管庁)
法務省:令和6年末現在における在留外国人数について
法務省:特定技能在留外国人数の公表等






賛否・中立の三点整理












まとめ/今後の見通し
三条市・JICA・慶應SFC研究所の連携協定は、地域おこしと国際協力を結びつける意欲的な取り組みです。ただし「定住促進」という表現が誤解を招き、移民政策との混同を引き起こしました。今後は発信の工夫と、地域住民への丁寧な説明が求められます。
国際協力と地域振興をどう調和させるか、日本全体で注目されるテーマとなりそうです。
三条市:三条市・国際協力機構・慶應義塾大学 SFC 研究所が
『地域おこしと国際協力の研究開発と推進に関する連携協定』を締結.PDF
よくある質問(FAQ)
Q:この協定は移民政策と関係あるのですか?
A:ありません。協定は地域おこしと国際研修を結びつけたもので、在留資格や永住制度とは無関係です。
Q:「定住促進」とは具体的に何を意味しますか?
A:外国人の永住を指すものではなく、地域に根差した人材育成や交流を促す意味で使われています。
Q:地域に外国人が増えることになるのですか?
A:国際研修生の受け入れはありますが、永住や大量移住を前提としたものではありません。
Q:住民にどのような影響がありますか?
A:研修や交流で国際色が増す一方、定住に誤解が生じると不安の声もあります。地域の理解と合意形成が重要です。


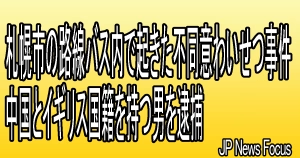
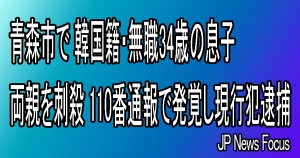
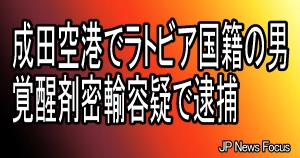
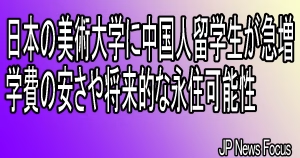
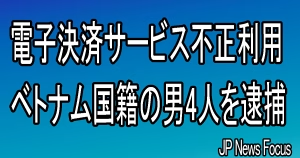
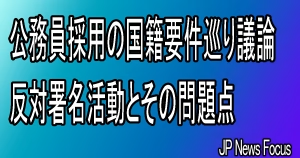
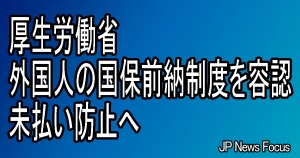
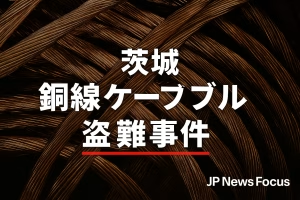
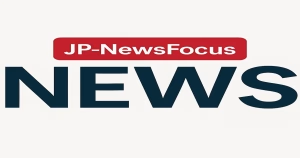
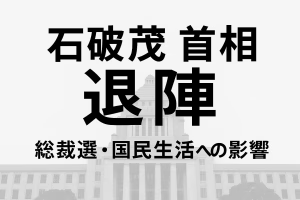

コメント