ニュース引用
日本政府は今後数年間でインド人5万人以上を受け入れる方針を固めた。モディ首相訪日に合わせ、経済・安全保障分野の連携とともに発表される見通しだ。
出典:朝日新聞
要約
日本政府は、インドとの経済・人的交流強化の一環として、今後数年でインド人5万人を受け入れる方針を打ち出した。対象はITや製造業、介護など幅広い分野とみられ、すでに在留する約5万4千人と同規模の追加受け入れとなる。背景には、日本の労働力不足とインドの若年人口増加がある。
インドは世界最大の人口を有し、特にITやエンジニアリング分野での人材供給国として注目されている。日本政府は、人口減少と高齢化が進む中で人材確保を急務としており、インドとの協力は戦略的意義が大きい。一方で、受け入れ方法は技能実習、特定技能、留学からの就職など複数の制度を組み合わせる必要があり、制度整備が課題となる。
また、急激な人口流入は社会的摩擦や治安への懸念を伴う。既存の外国人コミュニティとの共生や教育、住宅支援など、地域社会の受け入れ体制をどう構築するかが問われている。
統計・データ比較(グラフ・数値中心)
法務省によれば、2024年末の在留外国人数は約380万人。このうちインド人は5万4千人で全体の約1.4%を占める。政府が掲げる「5万人受け入れ」が実現すれば、インド人比率は倍増に近づく。
分野別では、インド人の多くはITエンジニアや高度専門職に集中しているが、今後は介護や製造業分野への拡大も見込まれる。観光庁の統計では、2024年に訪日したインド人観光客は約24万人に達しており、人的交流の基盤も拡大している。
背景(制度経緯と国際戦略)
日本は2019年に「特定技能制度」を導入し、外国人労働者の受け入れ枠を拡大した。近年はベトナムやフィリピンからの人材が中心だったが、政府はインドとの協定に基づき「包括的な人材パートナーシップ」を模索している。インドは若年人口が豊富で、2030年までに労働力の伸びが世界一と見込まれるため、日本にとって安定的な人材供給源となり得る。
さらに、外交戦略としても日印関係は重要性を増している。中国との関係が不安定化するなかで、インドとの協力を強めることは安全保障面でも意義が大きい。
関係者・地域の反応
経済界からは「高度人材の確保につながる」と歓迎の声が上がる一方、自治体や教育関係者からは「地域社会での共生策が追いついていない」と懸念も示されている。特に地方都市では、日本語教育や生活支援体制の不足が課題となっている。
宗教や価値観の違いと共生課題
インド社会は多宗教国家であり、ヒンドゥー教やイスラム教をはじめ、食習慣や生活文化に大きな違いがある。また、憲法上は廃止されたものの、カースト制度に由来する意識は現在も残っているとされ、海外のコミュニティでも序列意識や差別の問題が持ち込まれることがある。日本での受け入れが進む中で、こうした価値観の違いが地域社会との摩擦につながる懸念も指摘される。
一方で、インドの文化や祭礼が地域社会にもたらす多様性は、国際交流や経済活性化の契機ともなり得る。日本側が「差別を許容しない」と明確に示し、宗教や文化を尊重する受け入れ体制を整えることが不可欠だ。
SNSでの反応
- 「IT人材が増えれば日本経済にプラス」(肯定的意見)
- 「5万人は多すぎる。治安や文化摩擦が不安」(批判的意見)
- 「人口減少に対応するには当然の政策」(中立的意見)
- 「受け入れるなら日本語教育や住宅政策も同時に整えるべき」(建設的意見)
- 「外交戦略としてインドを重視するのは妥当」(国際関係視点)
全国的傾向とデータ
外国人労働者数は2023年に約200万人を突破。ベトナム、フィリピン、中国に次ぎ、インドも急増中だ。厚労省データによれば、外国人労働者のうち技能実習生が約35%、専門・技術分野が約20%を占める。インド人は高度人材比率が高いことが特徴であり、受け入れが進めば日本の労働市場構造に影響を与える可能性がある。
今回の方針は、単なる労働力補充ではなく、日本社会全体の多文化共生に関わるテーマといえる。
関連情報
カテゴリ:移民・在留制度/移民政策
タグ:India, 人材受け入れ, 日本政府, 移民政策, 在留資格, 特定技能, 外国人労働者, 多文化共生, 日印関係
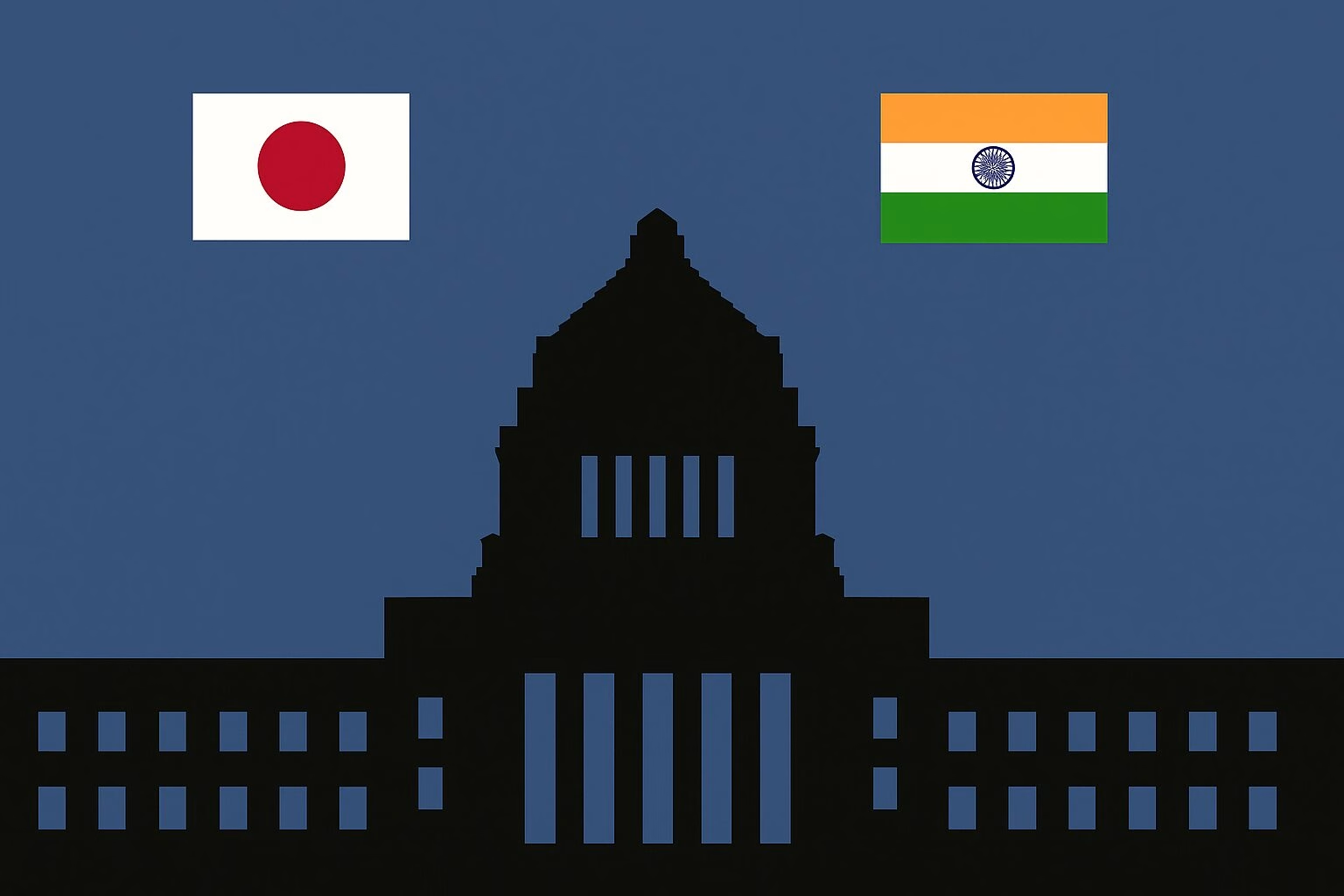
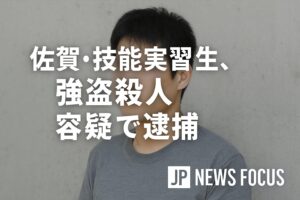

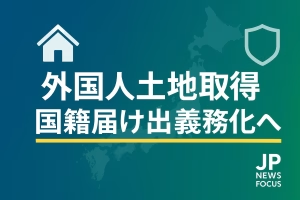
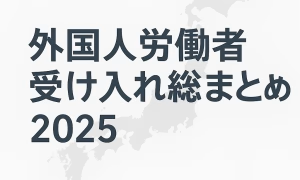

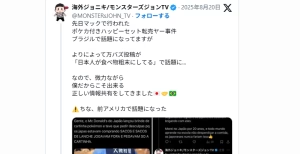
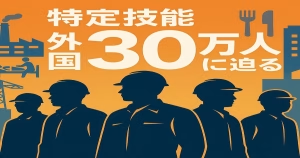
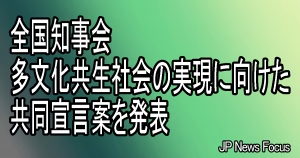

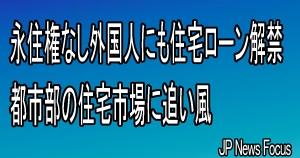
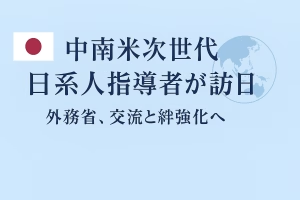
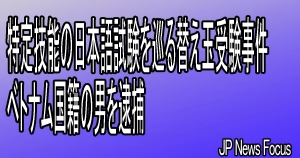
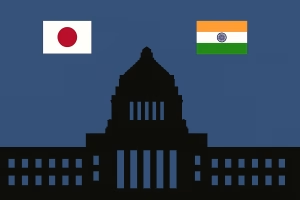
コメント