農水省は食品表示の「日本語+英語など」2カ国語併記を標準化する方針を示しました。輸出拡大と訪日外国人対応を狙う施策の背景、効果、課題を整理します。
制度導入の背景
農林水産省は2025年、日本食の海外展開と訪日外国人への対応を強化するため、食品表示の2カ国語併記を標準化する方針を打ち出しました。日本食輸出額は2023年に過去最高の1.4兆円を突破し、政府は2030年に2兆円を目標としています。一方、インバウンド需要も急回復しており、多言語対応の不十分さが課題とされてきました。(農水省公式サイト)
制度の内容
農水省の方針では、食品ラベルに日本語と英語など主要言語を併記することを原則化する方向で検討が進められています。今後は消費者庁が所管する 食品表示基準 との調整が行われ、段階的に制度化が進む見通しです。
期待される効果
特に農水省は、海外で日本食の模倣商品が流通するリスクを指摘しており、統一的な表記ルールは「日本産」のブランド保護にもつながるとしています。(JETRO 食品輸出動向)
課題と懸念
一方で、中小食品事業者にとっては翻訳作業や印刷コストの負担増が懸念されます。また、翻訳の精度や用語統一も課題です。例えば「しょうゆ」を “Soy Sauce” とするのか “Shoyu” とするのか、業界標準を整備する必要があります。加えて、輸出国ごとの規制に適合させる作業も不可欠となります。
賛否・中立の三点整理
賛成意見
・輸出拡大と訪日客対応の両立は国益に資する ・消費者にとって安全性と利便性が高まる ・国際標準化に沿ったルールで信頼が向上する
反対意見
・中小企業に翻訳や印刷コストの負担が大きい ・用語の統一が難しく混乱を招く恐れ ・制度導入が急すぎると現場対応が追いつかない
中立的視点
・世界市場に対応するためには避けられない流れ ・政府の支援策や段階的導入が不可欠 ・翻訳精度や監督体制をどう担保するかが焦点
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ














今後の展望
農水省は今後、消費者庁と連携して具体的なガイドラインを策定する予定です。食品輸出産業は成長戦略の柱とされ、2カ国語併記はその基盤整備の一環です。中小企業支援や翻訳ガイドラインの提供などが並行して進められるかが注目されます。

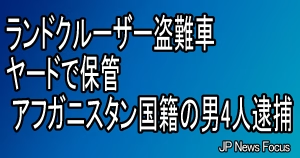

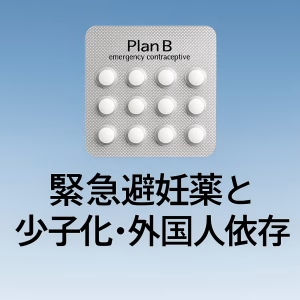
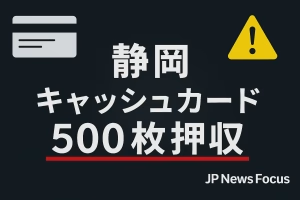
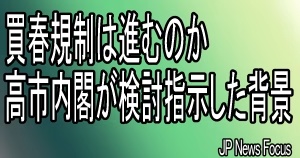
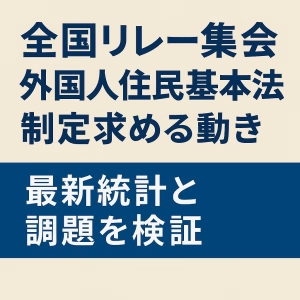
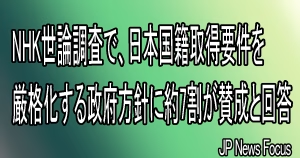
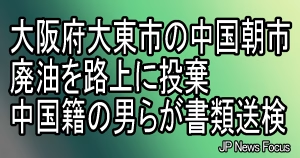
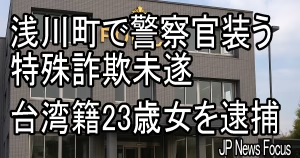

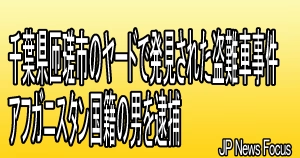
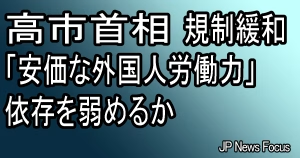
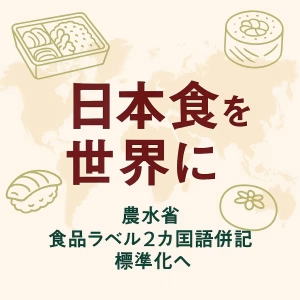
コメント