ニュース引用
共産党の田村智子委員長は都内での街頭演説で「極右排外主義が国会で多数を占めぬようにしなければならない」と述べ、聴衆からの抗議活動について「民主主義社会で当然認められるべき」と容認する姿勢を示した。
出典:朝日新聞
要約
共産党の田村智子委員長は、極右的な排外主義勢力が政治の中で台頭することを警戒し、街頭演説の場で抗議活動を容認する考えを示した。田村氏は「外国人排除を訴える勢力が多数を占めれば、日本の民主主義そのものが危うくなる」と指摘し、表現の自由の一環としての抗議を認める立場を強調した。
背景(過去事例・制度経緯)
街頭演説をめぐる抗議活動は過去にも論争を呼んできた。2019年の参院選では安倍晋三元首相の演説に対する抗議者を警察が排除し、後に「過剰介入ではないか」と批判を受けた事例がある。最高裁判例でも、選挙運動の自由と表現の自由の調整が課題として指摘されてきた。
また、日本国内では2010年代以降、排外主義的なデモやヘイトスピーチが社会問題化。川崎市など一部自治体は条例で規制を強化したが、国政レベルでは依然として「表現の自由」と「秩序維持」の線引きが曖昧なまま残されている。
解説・考察
田村委員長の発言は、表現の自由を広く認める立場に立ちつつも、「極右排外主義の伸長」への危機感が背景にある。外国人労働者や移民の増加に伴い、近年は「治安不安」「文化摩擦」を理由に排外的言説が拡散しており、国会でも一部議員が規制強化や制限を主張している。
一方で、抗議活動の容認は「選挙妨害を正当化するのか」との批判も呼んでいる。民主主義社会では異論の表明が重要だが、公共の場での秩序維持も必要であり、両者をどう調和させるかが大きな課題だ。
関係者・地域の反応
支持者からは「民主主義を守るために必要な姿勢」と評価する声がある一方、他党関係者からは「聴衆の安全や選挙の公正を軽視している」との批判も出ている。地域住民からも「抗議は認めても良いが、妨害と表現の自由は違う」といった冷静な意見が見られた。
SNSでの反応
- 「極右排外主義を牽制するのは必要。抗議の自由は民主主義の根幹」(支持)
- 「結局は選挙妨害を容認する危険な発言では」(批判)
- 「警察が過剰に排除しないよう歯止めが必要」(中立)
- 「排外主義を煽る政治家を放置する方がよほど危険」(支持)
- 「抗議活動をどう区別するのか基準が必要」(懸念)
全国的傾向とデータ
内閣府の調査によると「外国人と地域社会の共生」に賛成する割合は60%を超える一方、「治安や生活への影響が不安」と答える人も4割近い。外国人受け入れに対する社会の姿勢は二極化しており、政治家の発言や政策が世論に大きく影響している。
こうした背景のなかで田村委員長の発言は、民主主義と排外主義のせめぎ合いを浮き彫りにしたといえる。
関連情報
カテゴリ:国内ニュース/政治・政策
タグ:極右排外主義, 共産党, 田村智子, 抗議活動, 街頭演説, 表現の自由, 秩序維持, 外国人問題, 政治発言

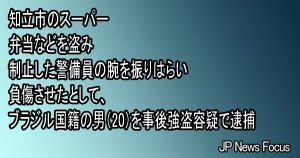
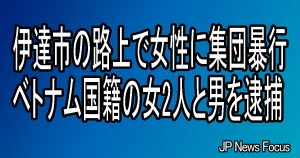
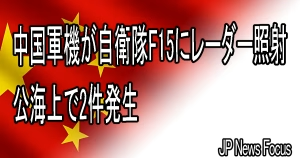
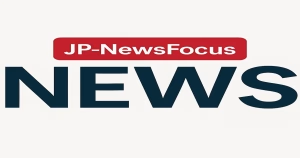
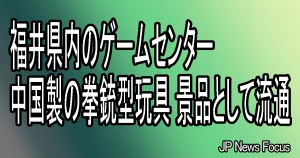
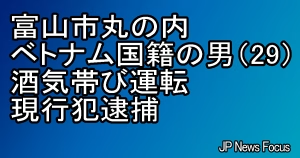
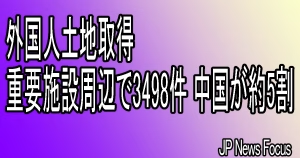
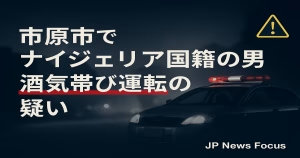
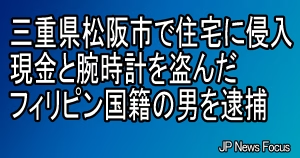
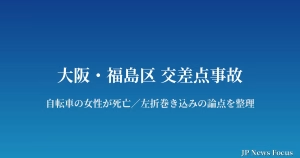
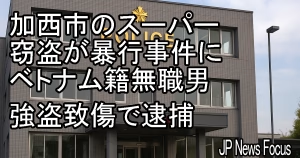

コメント