公開日:2025年8月31日 最終更新日:2025年9月8日 百田尚樹氏ら保守層からの批判、修正発言の意図と政策文脈を追加
参政党の神谷宗幣代表が移民受け入れ比率をめぐり「10%容認」から「5%以下」と表現を修正しました。支持者の反発が背景にあり、移民政策をめぐる国民的議論の難しさが浮き彫りとなっています。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ


参政党・神谷代表の発言経緯と修正
神谷代表は2025年8月下旬の演説で「移民を10%まで容認する」という趣旨を示しました。しかし、この数値は党支持層の反発を呼び、「単一民族の定義が崩れる」との批判が殺到しました。
その後、神谷代表は自身の公式Xで「外国を見ても移民が10%を超えたらとんでもないことになる」「今入れていいのは5%以下」と修正しました(神谷宗幣 公式X 2025年8月28日)。
YouTube参政党チャンネルでも「外国人受け入れには上限を設けるべき」と繰り返し述べており、今回の修正は支持層の声を踏まえた対応とみられます)。






日本と欧州の移民比率データ
法務省 出入国在留管理庁「在留外国人数」によれば、日本の在留外国人数は約343万人で、総人口比2.7%です。まだ10%には遠い状況です。
一方、イギリスは2021年時点で14%を超え、都市部では治安や社会摩擦が問題化しました(イギリス国家統計局 ONS)。フランスやドイツも10%を超え、同化政策の不足が摩擦拡大につながったとされています。
特にロンドンでは人口の4割以上が外国生まれであり、治安や教育負担、同化政策の難しさが指摘されています。欧州の事例は「急激な移民増加が社会不安を招く」典型例とされ、日本の議論に強い影響を与えています。






内部リンク:下村博文元文部科学相 東京都板橋区の小学校における外国籍児童の急増について言及
国内の現状と地域差
総務省の統計では、全国的には外国人比率は3%未満ですが、地域によっては大きく異なります。埼玉県蕨市では住民の約8%、静岡県浜松市では約8%が外国人住民。北海道の農業地域や九州の造船業地域でも技能実習生が集中し、比率が10%を超える地区があります。
こうした地域では、学校での日本語教育負担、医療通訳の需要、住宅環境の変化などが日常的な課題になっています。都市部と地方で体感の差があるため、「数字以上に存在感が大きい」との指摘があります。






※9月5更新情報
百田尚樹氏ら保守層からの批判
参政党・神谷宗幣代表の「移民10%容認」発言に対し、保守派から厳しい批判が相次ぎました。作家で日本保守党代表の百田尚樹氏は「1200万人の移民が入れば日本社会は確実に溶解する」と警鐘を鳴らし、神谷氏の発言を「一貫性を欠き、想像力に乏しい」と指摘しました(ニッカンスポーツ 2025年)。SNS上でも「数字を軽々しく扱うな」という声が広がり、党内外に波紋が広がっています。
修正発言の意図と政策文脈
その後、神谷氏は自身の公式Xで「移民はすでに飽和状態で、10%はあり得ない。現実的には5%以下に抑えるべき」と説明しました。背景には、高齢化ピーク期の労働力不足を一時的に補い、人口ピラミッドの安定後には外国人比率が自然減少するよう制度設計を行う意図があるとみられます(神谷宗幣 公式X 2025年)。Xトレンドではこの一連の発言をめぐり17万件以上の議論が確認されており、移民政策の数値表現がいかに支持層を刺激しやすいかを示す結果となりました(Xトレンド 2025年)。












神谷代表「移民比率5%以下」発言をめぐる視点


















FAQ:よくある疑問
Q:神谷代表はなぜ「10%容認」から「5%以下」に修正したのですか?
A:支持層から「単一民族の定義が崩れる」との強い批判が相次ぎ、保守層の反発を受けて修正したとみられます。本人は「現実的には5%以下が妥当」と説明しています。
Q:現在の日本の移民(在留外国人)比率はどのくらいですか?
A:2025年時点で約343万人で、総人口の2.7%程度です。全国平均ではまだ低い水準ですが、埼玉県蕨市や静岡県浜松市など一部地域では8〜10%を超えています。
Q:欧州の事例と比べて日本はどう違うのですか?
A:イギリスやフランス、ドイツでは移民比率が10%を超え、都市部では社会摩擦や治安問題が深刻化しました。日本はまだ比率が低いものの、急増すれば同様の課題が起きるとの警戒感が強いです。
まとめと今後の課題
神谷代表の「10%→5%」修正は、移民政策がどれほど支持者の神経を刺激するかを示しました。日本はまだ比率が低い一方で、欧州の失敗例は警戒を強める要因です。
今後は比率議論に偏らず、受け入れ体制の段階的整備と国民合意が不可欠です。国益を守る視点から、治安・教育・財政負担を含めた持続的な制度設計が求められ、受け入れ分野や条件を国民的に議論する必要があります。







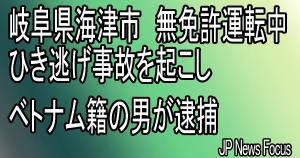
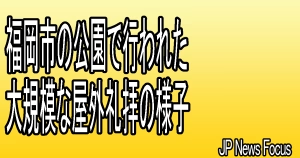
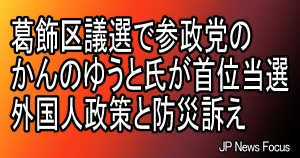
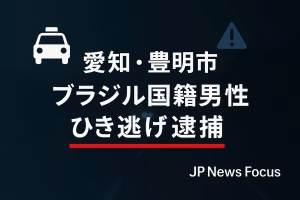
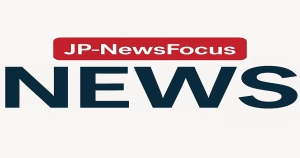
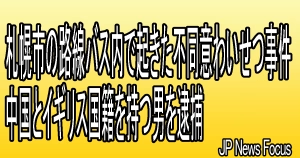

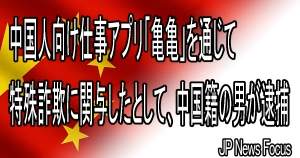
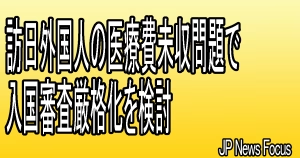
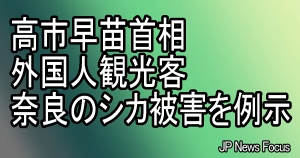
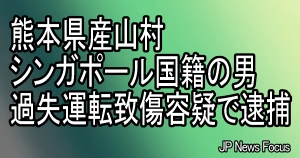

コメント