公開日:2025年9月6日|最終更新日:2025年9月9日
日本の人手不足対策の中心となっている「技能実習制度」と「特定技能制度」。これらは法務省や入管庁が所管する仕組みですが、実はJICA(国際協力機構)も人材育成や送り出し国支援を通じて深く関わっています。本記事では両制度の歴史と課題、JICAの役割、国際比較を整理し、日本社会にとってのリスクと可能性を検証します。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ


技能実習制度は1993年に始まり、当初は「途上国への技能移転」を目的としていました。しかし、実態は日本の労働力確保が中心となり、理念と現実の乖離が指摘されています。一方、2019年に導入された特定技能制度は、労働力不足を背景に「即戦力の外国人材確保」を明示的に目的としています(出入国在留管理庁 特定技能制度 2019)。
関連記事①:JICAとは 活動を解説 国際協力と日本社会への影響
JICAと技能実習制度の関与
JICAは技能実習制度の設計者ではありませんが、「技能移転」という理念が自らの国際協力方針と重なるため、関連調査や研修支援に関わってきました。例えば、ベトナムやインドネシアの職業訓練校に教材を提供し、建設分野の安全教育カリキュラム作成を支援しています(JICA 年次報告書2024)。






JICAと特定技能制度の取り組み
特定技能制度は2019年の入管法改正で創設され、今後5年間で最大35万人の受け入れが予定されました。対象分野は介護・建設・製造など人手不足が深刻な14分野です(厚生労働省 特定技能制度の概要 2024)。
JICAはこの制度に対して、送り出し国での職業訓練・日本語教育の支援を展開しています。フィリピンでは日本語教師養成プログラムを支援し、ベトナムでは日本語試験対策の教材を提供するなど、人材が来日前に基礎力を身につけられるよう環境整備を進めています。






JP-MIRAIと公正リクルートの推進
技能実習制度では「高額な送り出し手数料」や「ブローカーによる人権侵害」が国際的に問題視されてきました。こうした課題に対応するため、JICAは企業・自治体と連携して「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)」を設立しました(JICA JP-MIRAI 2020)。
JP-MIRAIでは、受入れ企業が法令遵守や人権尊重を徹底できるよう、指針や情報提供を行っています。これにより、過剰な費用負担や不当な扱いを防ぐ仕組みを整えつつあります。






外国人労働者数の推移と制度の限界
厚労省の統計によると、外国人労働者数は2023年10月末時点で約204万人となり、過去最多を更新しました(厚生労働省 外国人雇用状況統計 2023)。
こうした増加は制度の存在意義を裏付ける一方で、地域社会の負担や労働環境の懸念も指摘されています。持続的な制度運用には「透明性」「教育体制」「費用負担の適正化」といった要素が不可欠です。
賛否・中立の三点整理
賛成意見
JICAは法務省や出入国在留管理庁が制度設計を担う中、制度導入前後の外国人材に対するフォロー役として重要な役割を果たしており、送り出し国での人材育成を通じて質の高い人材確保を支えてきました(バックエンド「JICAと特定技能との関係は?」2025年8月29日)
反対意見
JICAの「アフリカ・ホームタウン」構想について、SNSでは「日本が乗っ取られる」「移民で埋め尽くされる」といった過激な表現が拡散し、市民からの抗議が各自治体へ殺到しました。住民の間には「交流ではなく移民誘導ではないか」という強い警戒感が生じました(東洋経済オンライン 2025年8月26日)。
The Guardian(2025年8月27日)も同様に、市や政府が相次いで「移民受け入れや特別ビザの発給は事実無根」と公式に否定した経緯を報じており、ソーシャルメディアを通じた過剰な反応と誤解の構造を詳しく伝えています。
中立・調整的立場
JICAの公式情報では、外国人材受け入れに関して自治体の支援体制が未整備である課題を提示しつつ、多文化共生に向けた“キーパーソンの育成”という中立的かつ建設的な政策提案が行われています(JICA公式 2025年)






他国制度との比較 ― 韓国・台湾との違い
外国人労働者の受け入れ制度は、日本だけの特例ではありません。韓国では2004年から「雇用許可制度(EPS)」を導入し、政府が直接送り出し国と契約して外国人労働者を管理しています。ブローカーを排除し、労働者保護を重視した制度設計が特徴です。
台湾でも「外国人労働者制度」に基づき、介護・建設分野などで多くの人材を受け入れています。日本との大きな違いは、受け入れがより明確に「労働力確保」を目的としており、技能移転を前提としていない点です。
これに対して日本の技能実習制度は「技能移転」を理念としながら、実態は労働力確保に傾いていると指摘されています。その矛盾を補う形で特定技能制度が導入されましたが、国際的には「制度を二重構造にする日本の特徴」が注目されています。












FAQ:よくある質問
Q:技能実習と特定技能の違いは?
A:技能実習は「技能移転」を理念とする制度ですが、実態は労働力確保に傾きがちです。一方、特定技能は2019年に創設され、人手不足を補う即戦力人材の受け入れを明確に目的としています。
Q:JICAは直接制度を作っているの?
A:制度設計は法務省や入管庁が担います。JICAは教育支援や送り出し国との協力、JP-MIRAIなどのプラットフォームを通じ、制度運用を補完する立場です。
Q:韓国や台湾と比べて日本の制度はどう違う?
A:韓国や台湾は「労働力確保」を目的に制度を設計しています。日本は「技能移転」を掲げつつ実態は労働力依存に傾くため、二重構造となっている点が特徴です。
JICA関連記事
関連記事①:JICAとは 活動を解説 国際協力と日本社会への影響
関連記事②:JICAと技能実習・特定技能制度 役割と日本社会への影響を解説
まとめ/今後の見通し
技能実習・特定技能制度は、日本の人手不足対策に不可欠な仕組みです。JICAは制度の設計主体ではないものの、送り出し国での教育支援や公正リクルート推進を通じて制度改善に寄与しています。
今後は、2030年に約77万人、2040年には約97万人の労働力不足が予測される中で、JICAの取り組みはさらに重要性を増すでしょう(JICA 年次報告書2024)。同時に、制度の透明性確保や地域社会の負担軽減をどう進めるかが、日本社会全体に問われています。
JICA関連記事
関連記事①:JICAとは 活動を解説 国際協力と日本社会への影響
関連記事②:JICAと技能実習・特定技能制度 役割と日本社会への影響を解説
次回は「組織編:外務省とJICAの関係」を取り上げ、制度を動かす構造を詳しく分析します。

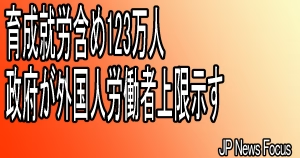

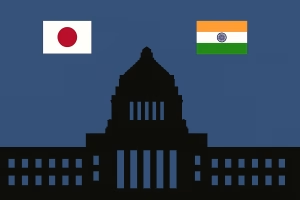
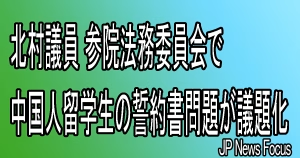

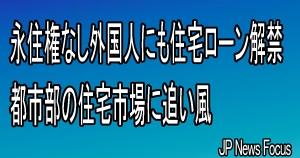
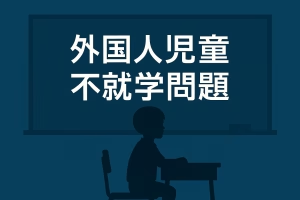
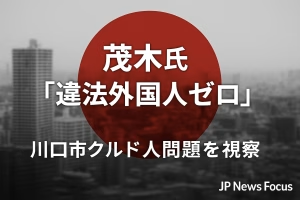

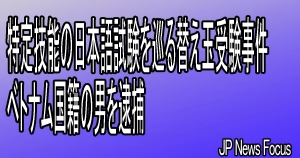

コメント