公開日:2025年9月11日 最終更新日:2025年9月11日
2025年現在、日本で暮らす外国人児童のうち「不就学」とされる子どもが全国で増加しています。文部科学省や自治体の調査では、言語の壁や家庭の経済状況、在留資格の制約が背景にあるとされ、日本社会の教育現場に大きな課題を投げかけています。本記事では、不就学問題の現状と影響、そして今後の見通しを整理します。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ





背景
日本に住む外国人は2024年末時点で約376.9万人に達しています。そのうち公立学校に在籍する外国人児童生徒は約12万9000人で、前年より約9%増加しました(nippon.com 2025)。一方で、日本語が十分に理解できず、学校に通えない「不就学」の子どもが存在し、教育格差の問題が顕在化しています。
文部科学省の資料(文科省 外国人児童生徒等教育の現状と課題 2024)では、不就学児童が一定数存在し、自治体間で大きな格差があることが指摘されています。
現状データ
外国人児童生徒の増加に伴い、日本語指導を必要とする子どもは全国で約5万人とされます(文科省 2024)。しかし、そのうち数千人規模は未だ学校に通っていないと推計されています。
要因としては以下が挙げられます。
・日本語教育体制の不足
・保護者が制度を理解できず、手続きが遅れる
・経済的理由により学用品や通学費用を負担できない
・在留資格や就労状況により就学が後回しにされる
関連記事:下村博文元文部科学相 東京都板橋区の小学校における外国籍児童の急増について言及


















地域・生活への影響
教育現場では日本語が理解できない子どもが増えることで、授業の遅れや教員の負担増につながっています。また、不就学のまま成長した場合、基礎学力の不足が将来的な就労機会の制限や生活保護依存の増加を招く恐れもあります。
住民からは「地域の学校に外国人の子どもが急に増えて対応が難しい」「保護者と意思疎通が取れない」といった声が聞かれます。SNS上でも「教育機会は保障すべき」「親の責任を国が肩代わりすべきではない」と賛否が分かれています。
海外事例比較:トルコにおけるシリア難民児の教育
日本の外国人児童不就学問題と似た課題は、海外でも見られます。代表例がトルコにおけるシリア難民児の教育統合です。シリア内戦以降、数百万人規模の難民がトルコに流入し、その中で子どもたちが教育を受けられない「不就学」が深刻化しました。
初期には言語の壁が大きく、トルコ語を理解できない子どもたちは授業についていけず、不就学状態が固定化するケースが多発しました。政府は特別教室や補習プログラムを設け、国際機関と連携しながら就学率を改善しましたが、地域ごとの格差や教員不足は依然として課題とされています。
この事例は、日本にとっても示唆的です。外国人児童の教育は「初期対応が遅れると不就学が長期化する」点で共通しており、早期の日本語指導や生活支援が将来の社会安定に直結することを示しています。
出典:ScienceDirect「Integrating Syrian refugee children in Turkey」(2020)






賛否・中立の三点整理
賛成意見
教育機会の保障は人権上当然であり、日本語教育を通じて社会参加を促すことは長期的に日本社会の安定につながる。
反対意見
税金で支援することは不公平であり、保護者の責任を国が肩代わりするべきではない。自治体や学校への負担が過大である。
中立・調整的立場
義務教育の対象や制度を整理し、自治体や教育現場に過度な負担をかけず、国の財政支援や制度設計を見直すことが必要。















外国人児童不就学問題のまとめと今後の見通し
外国人児童の不就学問題は、教育現場だけでなく社会全体の安定に関わる課題です。日本語教育の体制を拡充すると同時に、家庭や地域と連携して学習機会を確保することが求められます。
外国人が総人口の1割に達する可能性が指摘されています(朝日新聞 2024)。今後は政府や自治体が制度的に持続可能な支援策を整備できるかが焦点となります。文部科学省や法務省の合同会議の動向に注視する必要があります。












内部リンク:入管庁が不法残留者の増加を公表 埼玉・愛知・東京に集中
FAQ
Q:外国人児童の不就学はどのくらいの規模ですか?
A:正確な数は自治体によって異なりますが、全国的に数千人規模と推計され、日本語教育支援の不足が主な要因とされています。
Q:不就学が社会に与える影響は?
A:基礎学力不足による就労制限、生活保護依存のリスク増加、地域社会での摩擦などが懸念されます。
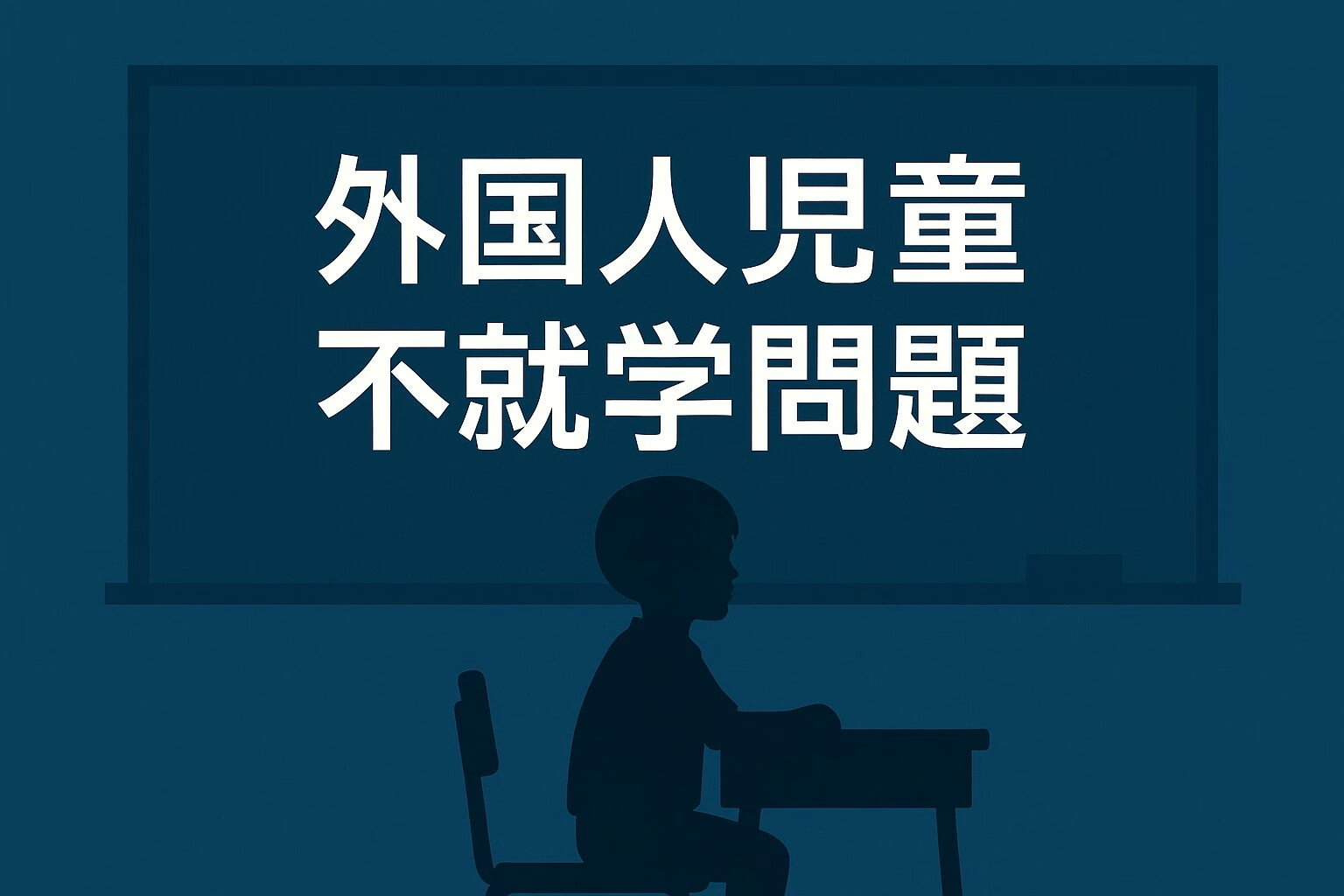
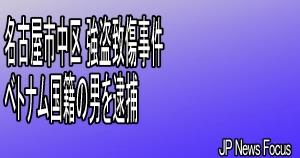
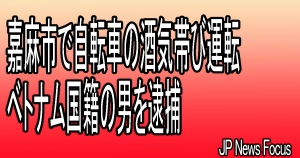
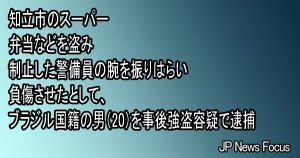
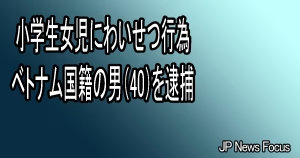
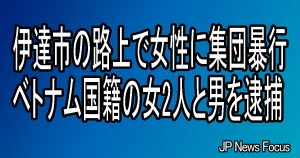
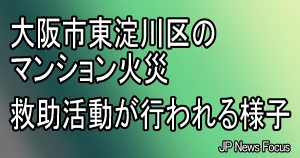

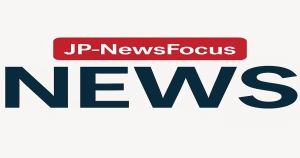


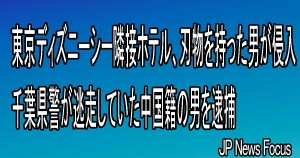
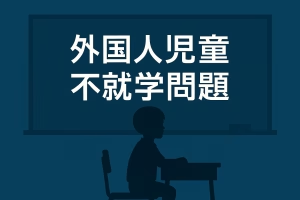
コメント