公開日:2025年8月29日 最終更新日:2025年9月9日
厚生労働省は2025年8月、緊急避妊薬(ノルレボ錠など)を薬局で処方箋なしに購入できる制度を決定しました。年齢制限や親の同意は不要で、薬剤師の対面販売と面前服用を必須とする仕組みです。背景には性暴力や予期せぬ妊娠への迅速対応の必要性があり、試験販売の結果を踏まえて制度化されました(沖縄タイムス 2025)。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ


少子化と人口構造の現状
日本は急速な少子高齢化が進行しています。2024年に日本人人口は前年比で約90万人減少し、65歳以上の割合は29.1%に達しました。労働力人口(15〜64歳)は1995年の8,726万人をピークに縮小し、2024年には7,373万人まで減少しました(パーソル総研 2025)。






外国人労働者の増加と依存
労働力不足を補うため、外国人労働者は増加傾向にあります。2023年10月末時点で約205万人、2024年には230万人を超えました。特に製造業・介護・サービス業で依存度が顕著となっています(内閣府白書 2024)。






制度と外国人依存の間にある因果構造
緊急避妊薬市販化と人口動態は直接の因果関係ではありませんが、次のような構造的連関があります。
・避妊薬利用拡大 → 出生率低下の一因
・出生率低下 → 労働力人口減少
・労働力人口減少 → 外国人労働力依存度上昇
制度の趣旨は人権支援ですが、人口動態と重なると「避妊薬普及→少子化深化→外国人依存」という連鎖のリスクをはらんでいます。






制度運営上の課題
新制度には運営上の課題も指摘されています。
・面前服用の心理的負担
・薬局の地域差によるアクセス格差
・買い溜めや国外転売の懸念
・薬剤師の説明や啓発の質の確保
これらの課題を解決できなければ、制度は形骸化し、社会的信頼を損なう可能性もあります。
(参考資料:朝日新聞、Japan Times)






専門家の視点と制度への提言
厚生労働科学特別研究事業(2025年)の報告によれば、日本産婦人科医会は「緊急避妊薬の購入者の86%が服用後に産婦人科を受診していない」と指摘。OTC化後も同様の傾向が続くと見られるため、「妊娠のリスク」を念頭に置きつつ、必要に応じて速やかに医療機関につながるよう使用者に丁寧に案内すべきであるとしています。薬剤師には、「妊娠の可能性」を的確に判断できる研修の整備が不可欠とされています。
(厚生労働省)






国益的視点での示唆
緊急避妊薬制度は人権の観点で評価できますが、少子化対策・移民政策と切り離しては議論できません。出生率低下を放置すれば、外国人依存の連鎖が強まる可能性があります。教育・啓発と安全な流通管理を並行し、人口政策の一環として総合的に捉える必要があります。






国際比較と教訓
米国では移民が労働力人口を底上げし、成長を支えています。一方、欧州では避妊薬普及と移民依存が並行して進み、地域社会で摩擦を生んだ事例もあります。制度設計には両面の教訓を反映させることが求められます(WSJ 2024)。






巷に広がる「外国人対策」との誤解
ネット上では「外国人による性犯罪が増えるから避妊薬が必要なのでは」との声も見られます。しかし制度の本来目的は性暴力被害や避妊失敗時の救済であり、国籍を特定した対策ではありません。
(参考資料:厚生労働省・評価部会資料:誤解への懸念と現場の声)


















FAQ:よくある疑問
Q:緊急避妊薬の市販化は少子化に影響しますか?
A:直接的な因果関係はありません。制度の目的は性暴力や避妊失敗時の救済です。ただし、避妊薬の利用拡大が出生率に間接的な影響を与える可能性はあり、人口政策全体の中で議論する必要があります。
Q:この制度は外国人対策のためなのですか?
A:いいえ。厚生労働省の説明では、制度の目的はあくまで「性暴力や予期せぬ妊娠への迅速対応」であり、国籍を特定したものではありません。ネット上にある「外国人犯罪と結びつける見方」は誤解です。
Q:購入するときに注意すべき点は?
A:薬剤師による対面販売と面前服用が必須で、買い溜めや転売は禁止されています。服用後も妊娠の可能性はゼロではないため、必要に応じて産婦人科の受診につなげることが重要です。
まとめ
緊急避妊薬の市販化は人権支援策として評価できる一方、少子化・外国人依存との連関を無視できません。医療・教育・人口政策を統合的に設計し、制度の持続性と国益を守るバランスが必要です。
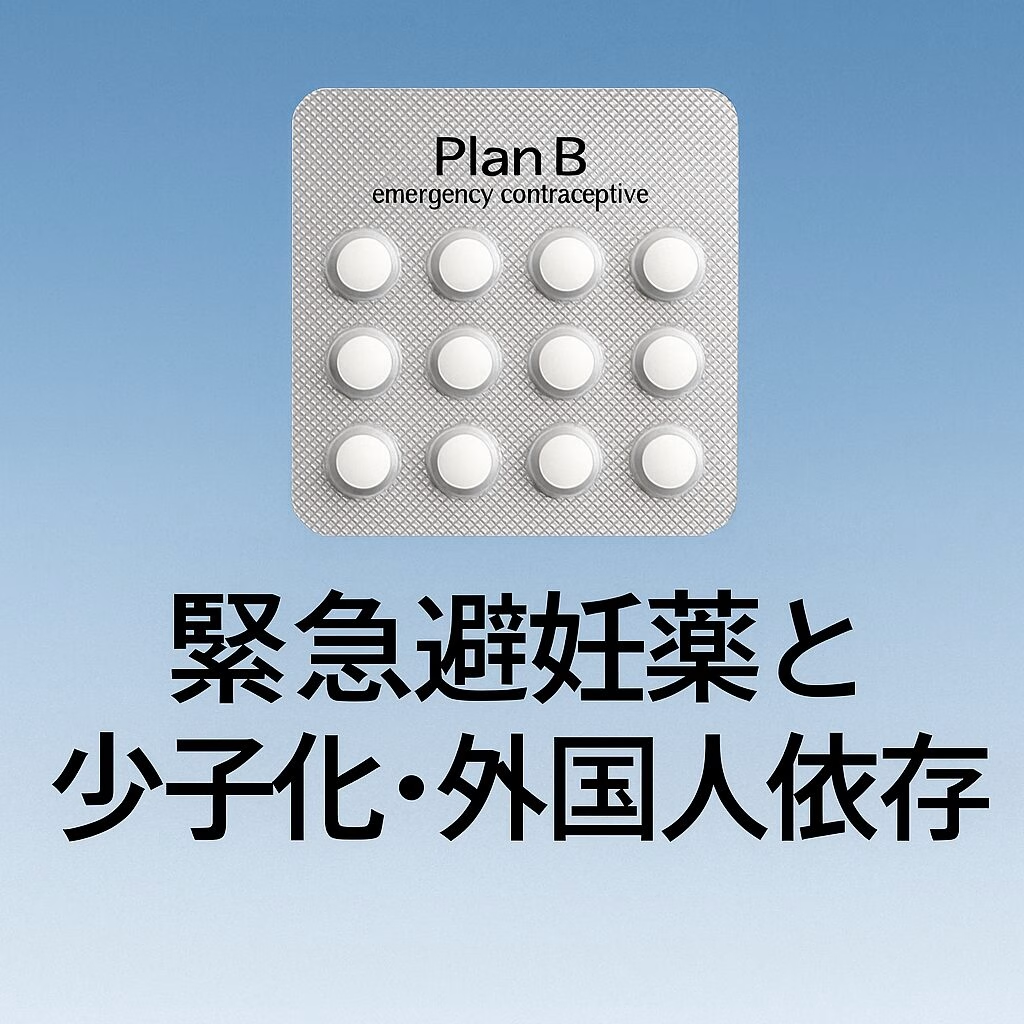
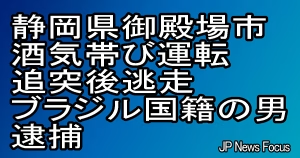

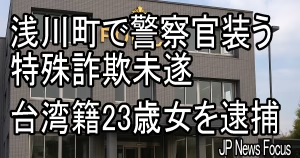

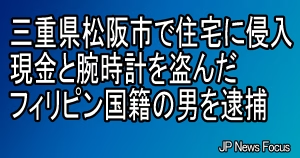
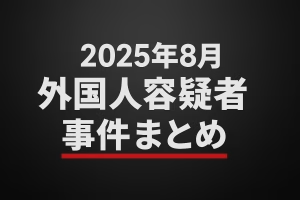
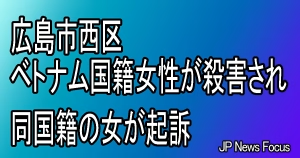
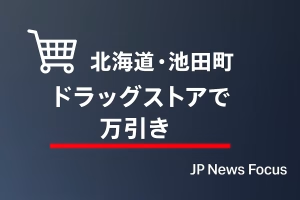
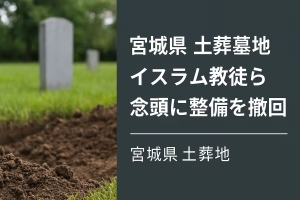
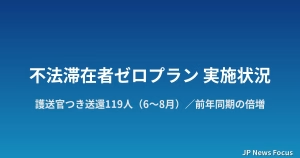
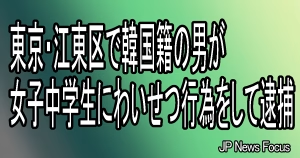
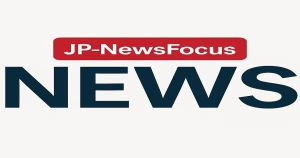
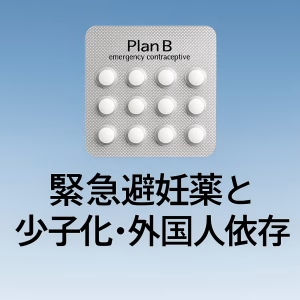
コメント