公開日:2025年8月28日 最終更新日:2025年9月16日
日本とバングラデシュは2025年8月、人材交流促進に関する覚書(MoU)を署名しました。文書には「今後5年間で10万人規模の人材受け入れ」の方針が記されており、介護・建設・製造・農業など人手不足分野を対象としています。(Dhaka Tribune 2025/08/26)
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ


【ポイント】
- 日本とバングラデシュが「10万人規模の人材受け入れ」で覚書を署名
- 介護・建設・製造など人手不足分野に集中配置
- 地域社会や教育・医療への影響が課題に
MoUの内容と受け入れ分野
覚書の対象は技能実習(TITP)と特定技能(SSW)です。特に介護、建設、製造業で人手不足が深刻化しており、優先的に人材を配置する方針です。バングラデシュ政府は送り出し体制を強化、日本政府は受け入れ企業や監理団体に対する監督を強めるとしています。
(参考資料:Tha Business Standard2025)






現状のデータと規模感
法務省の統計によれば、2024年末の在留バングラデシュ人数は約5万人で、在留外国人全体の1.5%程度にとどまります(法務省 在留外国人統計 2024)。留学生は2023年に約3,000人(JASSO 2023)、技能実習生は2023年に約9,000人(入管庁統計)。
外国人労働者全体は2024年10月末で230万人。国籍別ではベトナム約54万人、中国約39万人、フィリピン約22万人。バングラデシュ人は数万人規模に過ぎませんが、新たに10万人を加えれば全体の4〜5%を占め、上位国に近づく規模感です(厚労省 外国人雇用状況 2024)。






内部リンク:板橋区小学校で外国籍児童倍増 予算増額と国際比較から見える課題
地方社会と生活への影響
新たな労働者の多くは、建設や製造拠点のある地方都市に配置される見込みです。群馬県や愛知県ではバングラデシュ人住民が増加し、教育・医療・住宅など生活基盤への対応が課題となっています。川口市では宗教儀礼や食習慣への対応が地域社会の焦点となっており、ハラール対応食材や礼拝場所の整備が進みつつあります。






関連記事:今治市など4自治体、アフリカ各国のホームタウン認定 今後起こり得る影響とは?
日バングラデシュ人材MoUをめぐる視点


















今後の制度改革と見通し
MoU署名は枠組みにすぎず、実際の受け入れは2025年末以降と見込まれます。2027年には技能実習制度が廃止され、新制度「育成就労制度」へ移行予定であり、バングラデシュ人材も対象となる可能性があります(法務省 育成就労制度告示)。段階的に人材受け入れが拡大していく見通しです。






専門家の視点:労働市場と人口政策
労働経済学者は「10万人規模の受け入れは日本の労働市場に短期的な安定をもたらすが、賃金水準や雇用条件に影響を与える可能性もある」と指摘しています。一方、人口学者は「移民政策は少子化対策の代替ではなく補完策であるべき。出生率回復と並行して設計されなければ持続性を欠く」と警鐘を鳴らしています。






FAQ:よくある疑問
Q:10万人の受け入れは本当に実現するのですか?
A:MoU(覚書)は法的拘束力がないため、必ず10万人が来日するとは限りません。実際の人数は制度運用や企業ニーズ、地域の受け入れ体制によって調整されます。
Q:受け入れ分野はどこが中心になりますか?
A:介護・建設・製造・農業など、人手不足が深刻な分野が中心です。特に介護や建設は即戦力として期待される一方で、教育や生活支援の体制整備が課題となります。
Q:地域社会への影響はどのように出るのですか?
A:住宅や医療、学校教育など生活基盤への負担が増す可能性があります。一方で、地域経済の活性化や産業の持続性にはプラス効果が見込まれます。川口市ではハラール対応食材や礼拝場所の整備が進んでおり、文化的な調整も不可欠です。
Q:10万人の受け入れはいつから始まりますか?
A:MoU署名は2025年8月ですが、実際の受け入れは2025年末以降と見込まれています。2027年には技能実習制度が廃止され、新制度「育成就労制度」に移行予定で、この流れと連動して人数が増える可能性があります。
Q:なぜバングラデシュなのですか?
A:人口増加率が高く労働力が豊富で、日本語教育や送り出し体制を整えているためです。さらに、日本政府とバングラデシュ政府の間で人材協力関係が強化されていることも背景にあります。
まとめ
日本とバングラデシュの「10万人受け入れ」合意は、単なる人材確保策にとどまらず、日本社会の制度と生活基盤に大きな影響を与えます。公的統計を裏付けにしつつ、地域社会の声や国際比較を踏まえることで、制度の持続性を検証していく必要があり、制度改革と地域対応の両立が不可欠です。
総括:日本にとってリスクとメリット












最新の進捗について 2025年9月16日更新
覚書署名後、いくつか具体的な動きが明らかになってきました。
たとえば、特定技能教育と日本語教育を含む研修体制整備に向けて、企業「ONODERA USER RUN」がバングラデシュ政府機関(BMETなど)とMOUを締結。現地で教育拠点を設けるなど、送り出し体制強化の動きがあります。
(参考:ONODERA USER RUN プレスリリース)
また、日本外務省の覚書署名関連文書には人材育成・送り出しに関する協力の枠組みが示されており、制度的な準備が進んでいることが確認できます。
(出典:外務省「日・バングラデシュ覚書署名」(PDF, 2025年8月26日))
ただし、10万人計画に対する受け入れ実績の数字や年間スケジュールなど、法務省や厚生労働省からの公式な進捗報告はまだ公開されていません。
(参考:法務省 出入国在留管理庁「特定技能 在留資格制度」、厚労省「外国人雇用状況(2024年10月末)」)
ONODERA USER RUN のプレスリリースでは、単なる技能実習生の送り出しにとどまらず、現地教育から日本での定着支援まで一貫した仕組みが打ち出されています。これは短期滞在というより「長期的な移住モデル」に近い計画であり、制度設計のあり方をめぐって議論を呼びそうです。












内部リンク:技能実習制度から特定技能への移行者 過去最多を更新
関連情報:法務省 在留外国人統計

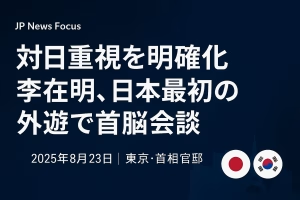
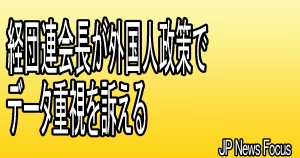



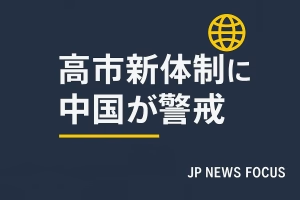



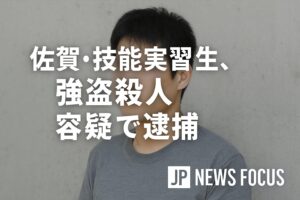
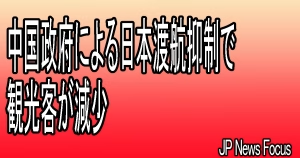

コメント