公開日:2025年8月17日 最終更新日:2025年9月10日
火葬が主流の日本で、宗教的理由から土葬を望む外国人遺族が、受け入れ墓地の不足から無許可で「闇土葬」を行うケースが問題化しています。衛生上の懸念、地域住民の反発、制度の未整備が複雑に絡み合うこの課題は、外国人増加と多文化共生の進展に直結しています。本稿では現状データ、地域の声、海外比較を交えて、闇土葬問題を多角的に検証します。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ





背景と現状
日本では「墓地、埋葬等に関する法律」で土葬は認められていますが、許可を得た墓地に限られます。実際には火葬率が99.97%(2022年、厚労省)に達しており、全国で土葬が可能な墓地は十数カ所しかありません。そのためイスラム教徒など一部宗教の遺族が正式な墓地を利用できず、やむを得ず無許可の「闇土葬」が行われています。
厚労省の調査によれば、自治体の大多数は「土葬墓地の新設予定はない」と回答しており、需要と供給の乖離が広がっています。
出典:厚生労働省「墓地、埋葬時に関する法律」1948年
出典:札幌の葬儀・家族葬ならウィズハウス






地域・生活への影響
埼玉県本庄市の霊園では土葬区画を設けていますが、管理費未払い・無断埋葬といったトラブルが報告されています。大分県日出町で計画されたムスリム墓地は住民の反対で頓挫。宮城県内でも整備計画に対しSNSで「理解はするが近所には欲しくない」といった声が目立っています。
出典:おはかんり「【レポート】埼玉の土葬墓地「本庄児玉聖地霊園」に見る多様なお墓の風景」












全国的傾向と統計
法務省統計によれば、2024年末の在留外国人数は約322万人で過去最多。うちイスラム教徒は推計23万人とされ、潜在的な土葬需要は小さくありません。しかし制度が追いつかず、違法状態を招いています。
厚労省の最新調査では、自治体の約8割が「土葬墓地新設に否定的」と回答しており、政策的な対応が遅れていることが明らかになりました。
出典:法務省「在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表 2024」






海外事例との比較
フランスでは公共墓地に「ムスリム区画」を設置可能。イギリスでも宗教別の埋葬形態を尊重する制度があります。これに対し日本は火葬一律が慣習化しており、例外を認めにくい構造を持つため、多文化対応の遅れが指摘されます。
出典:Wikipedia「Bobigny cemetery」






宗教団体・NPOのコメント
日本イスラム文化センターは「土葬は信仰の根幹に関わる行為であり、日本に住む信徒にも配慮が必要」とコメント。NPOも「制度の未整備が違法行為を誘発している」と警鐘を鳴らしました。また経済的理由から火葬を選べない遺族がいることも問題とされています。
出典:朝日新聞「土葬できる墓地、ムスリムの申し込み途切れず かつての風習つなぐ」






関連記事:技能実習制度から特定技能への移行者 過去最多を更新
自治体の対応
宮城県内では多文化共生を目的とした「土葬対応墓地」の検討が始まりました。埼玉県の一部霊園では行政と連携し「土葬マニュアル」を作成し、埋葬方法を多言語で説明しています。こうした試行は全国的な制度改革の先駆けとなる可能性があります。
出典:河北新報オンライン「「日本で土葬はできない」ってウソ?ホント? ムスリム対応で物議…ネット情報の真偽を調べる<かほQチェック>」






賛否・中立の三点整理












まとめ/今後の見通し
闇土葬問題は、宗教の自由・地域の安心・衛生基準・多文化共生が交錯する複雑な課題です。現状を放置すれば、法的トラブルや住民摩擦の増加が懸念されます。
解決には、①外国人コミュニティとの対話、②受け入れ墓地の整備、③地域住民との合意形成、④衛生基準の策定が不可欠です。外国人受け入れを進める日本にとって、葬送制度の見直しは避けられない課題です。






よくある質問(FAQ)
Q:日本では土葬は禁止されているのですか?
A:禁止されていませんが、許可を受けた墓地内でのみ認められます。実際には火葬が主流で土葬墓地はごくわずかです。
Q:なぜ闇土葬が発生するのですか?
A:宗教的に火葬が認められない人々が、正式な土葬墓地を利用できず無許可埋葬を行うためです。
Q:どのくらいの外国人が土葬を希望するのですか?
A:在留外国人322万人のうち、イスラム教徒は推計23万人とされ、一定数の需要があります。
Q:解決策はありますか?
A:墓地の受け入れ整備、衛生基準の明確化、地域住民の理解促進などが必要です。

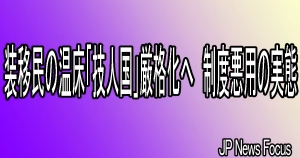
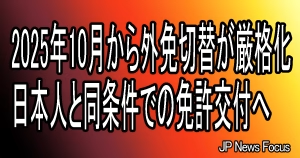
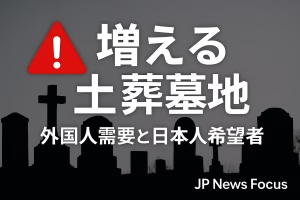
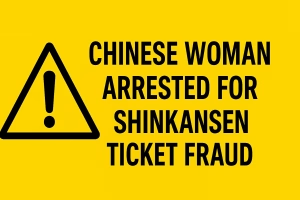
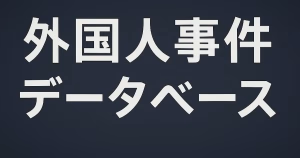

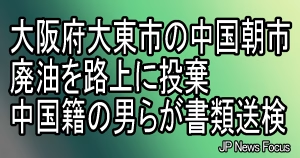
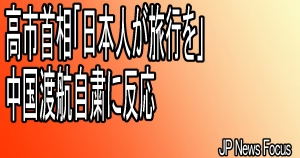
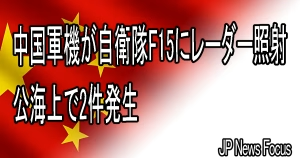
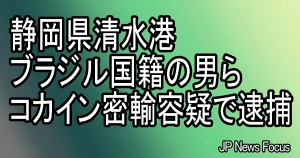



コメント