北海道・釧路湿原で進むメガソーラー開発をめぐり、2025年9月に大きな動きがありました。北海道は森林法に基づく許可を得ないまま工事を進めたとして事業者の工事を違法と認定し、一部中止を勧告。さらに釧路市は太陽光発電施設を許可制とする新条例案を市議会に提出しました。国際的に保護される湿地と再エネ政策の両立が、改めて鋭く問われています。(公開日2025年9月2日・最終更新日2025年9月8日)
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ


釧路湿原メガソーラー 工事違法認定と中止勧告
2025年9月2日、北海道釧路総合振興局は、大阪市の事業者「日本エコロジー」が森林法に基づく許可を得ずに工事を進めていたとして、約0.8ヘクタールの区域を違法工事と認定し、工事の一部中止を勧告しました。事業者は該当区域での工事を停止したものの、事業全体は継続の意向を崩していません。 北海道新聞 2025 ITmediaニュース 2025






釧路市 太陽光条例案提出と許可制導入
2025年9月4日、釧路市は太陽光発電施設を規制する新条例案を市議会に提出しました。主な内容は以下の通りです。
・出力10kW以上の事業用太陽光発電を届け出制から許可制に変更
・タンチョウなど希少な5種を「特定保全種」に指定
・生息可能性の高い区域を「特別保全区域」とし、生息調査や保全計画の提出を義務付け
・保全措置を講じない場合は建設を許可しない
・施行は2026年1月1日以降の案件が対象(進行中案件は適用外)






背景:開発計画の経緯と地域の自然保護運動
釧路湿原は日本最大の湿地で、総面積約2万8千ヘクタールを誇ります。ラムサール条約に登録されており、タンチョウをはじめとする絶滅危惧種の生息地でもあります。近年、再生可能エネルギー導入を背景に、湿原近隣でのメガソーラー建設計画が浮上しました。事業者は数十億円規模の投資を表明し、設置面積は数十ヘクタールに及ぶと報じられています。
しかし、計画公表当初から自然保護団体や研究者は強く反発しました。市民団体は「湿地生態系の回復努力を台無しにする」と警鐘を鳴らし、釧路市議会でも住民請願が取り上げられました。これまでの反対運動は、国立公園内での大規模開発をどう規制するかという課題を浮き彫りにしてきました。
内部リンク:外国人住民基本法と全国リレー集会 最新動向と日本社会への影響
現状データ:環境省・北海道庁の調査データ、再エネ導入率
北海道は全国でも再エネ導入が進んでいる地域です。北海道庁の統計によると、2015年度時点で太陽光発電の電源比率は約7%でしたが、2023年度には17%まで拡大しました。風力も同期間で5%から12%に上昇し、北海道全体の電源構成に占める再エネ比率は着実に増加しています。
一方、釧路湿原周辺は観光資源としても重要です。釧路市観光統計によると、2023年の観光入込客数は約260万人に達し、観光収入は数百億円規模にのぼります。特にエコツーリズムやタンチョウ観察は国内外からの誘客につながっています。
漁業面では、釧路川水系に依存するサケやシシャモの漁獲量が地域経済を支えており、環境省の調査では水質悪化や日照条件の変化が漁業資源に影響する可能性が指摘されています。また、タンチョウ・イトウなどの希少種が環境省レッドリストに掲載されており、湿原の保全価値は国際的にも極めて高いとされています。












地域・生活への影響
釧路湿原周辺でのメガソーラー建設をめぐり、住民からは「安全が確保されない限り市有地を貸さない」との要望が出されています(北海道新聞 2025年8月)。市長も「自然との調和を欠く太陽光発電施設は望まない」と述べ、条例化に踏み切る姿勢を示しました(朝日新聞 2025年5月)。
一方で、事業者は「繁殖期を避ければ希少生物への影響は小さい」と説明し、住民との意見が分かれています(HTB北海道ニュース)。また、専門家からは景観や廃棄リスクなど全国的に指摘される課題が釧路でも顕在化していると警鐘が鳴らされています(弁護士JP)。
このように、自然環境・安全・エネルギー政策が交差する中で、地域住民の生活や将来像に直結する議論が広がっています。












政策文脈:再エネ政策と国立公園保護の狭間
日本政府はGX実行会議において、2030年までに再エネ比率36〜38%を達成する目標を掲げています。その達成に向け、各地でメガソーラーや風力発電の建設が進められています。しかし、国立公園や自然保護区における大規模開発には、保護との整合性が問われます。
再エネ特措法(固定価格買取制度:FIT)は投資促進に寄与しましたが、一方で「環境影響評価が十分でないまま開発が進む」との批判もあります。環境省内部でも「国立公園内での再エネ開発規制」をめぐる議論があり、規制強化の是非が検討されています。












海外比較:ドイツとアメリカの再エネと自然保護の調整
ドイツではソーラー施設を景観や希少種への影響まで考慮し、行政と研究機関が協力して配置設計や基準づくりを進めています(Energy, Sustainability and Society, 2020)。一方、アメリカ・カリフォルニア州では砂漠地帯の大規模ソーラー建設が環境団体と衝突し、訴訟や規模縮小を経て、保護区の設定や建設区域の限定といった妥協策が取られました(AP通信, 2016)。両国の経験は「事前の科学的評価」と「住民・環境団体との対話」が不可欠であることを示しています。これに比べ日本の湿地は国際的保護義務を伴うため、さらに慎重な判断と国際社会に対する説明責任が求められるといえるでしょう。









釧路湿原メガソーラーをめぐる視点


















まとめ/今後の見通し
今回の違法工事認定と条例案提出は、釧路湿原メガソーラー計画にとって大きな転機です。条例が成立すれば新規案件への規制は強まり、事業者の工事継続も困難になる可能性があります。生態系保全、住民合意、国のGX目標の調整という三つの視点から、今後の審査や議会の行方が注目されます。
当サイトでは条例審議や住民説明会の進展を追い、随時追補更新を行っていきます。
よくある質問(FAQ)
Q:釧路湿原メガソーラーは中止されるの?
A:現時点では一部工事が中止されただけで、事業全体は継続の方針です。ただし、条例案の可決や住民合意の行方次第で、計画が縮小や延期となる可能性があります。
Q:条例が成立すると何が変わるの?
A:条例が成立すれば、出力10kW以上の太陽光発電は許可制となり、タンチョウなど希少種の保全措置が義務付けられます。これにより、無秩序なメガソーラー建設は大幅に制限される見込みです。







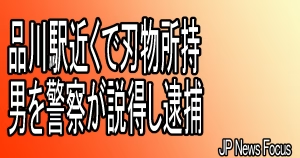
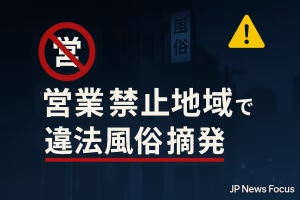
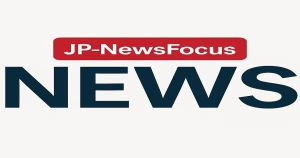
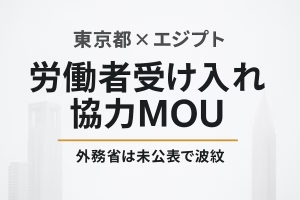
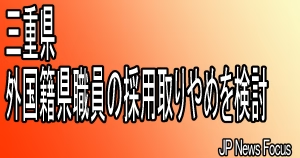
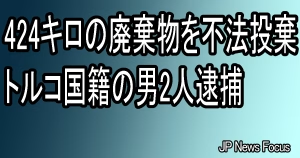
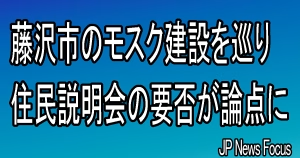
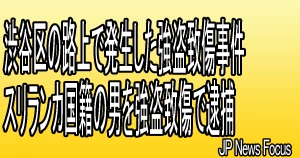
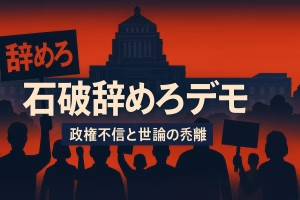
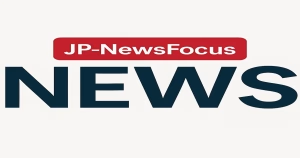

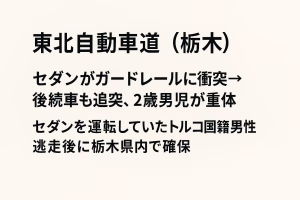

コメント