公開日:2025年9月4日|最終更新日:2025年9月8日
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ








JICA(独立行政法人国際協力機構)は「開発途上国への支援機関」として広く知られています。しかし、その活動は海外にとどまらず、日本国内における外国人材の受け入れや多文化共生にも直結しています。本記事ではJICAの概要と事業領域を整理し、日本社会にどのような影響を与えているのかを解説します。
JICAとは何か ― 国際協力と外国人受け入れの役割
設立の経緯と組織概要
JICAは外務省所管の独立行政法人として2003年に設立されました。前身は「海外技術協力事業団(1984)(OTCA)」や「国際協力事業団」などで、長年にわたり日本の政府開発援助(ODA)を担ってきました。組織の目的は、開発途上国の経済社会発展を支援し、国際社会の安定に寄与することとされています。詳細は JICA 公式サイト(組織概要 2025) をご参照ください。
国際協力の主要事業
JICAは「技術協力」「有償資金協力」「無償資金協力」の三本柱を展開しています。たとえば青年海外協力隊の派遣やインフラ整備支援、農業・医療・教育分野での協力プロジェクトなどが代表例です。外務省の外交政策を支える実行部隊でもあり、日本の国際的な存在感を示す役割を担っています。具体的な事業内容は JICA 年次報告書2024 にまとめられています。
関連記事:技能実習制度から特定技能への移行者 過去最多を更新






補足:年間予算と職員数
2024年度のJICA予算は約1兆2,000億円(外務省ODA関連予算を含む)で、職員数は国内外合わせて約1,900人です。これにより国際協力分野では世界有数の規模を誇ります。
JICAと外国人受け入れ・人材交流の実態
研修員・留学生の受け入れ
JICAは毎年多くの研修員・留学生を日本に受け入れています。2022年度には約7,800人が来日し、工学・保健医療・行政管理など幅広い研修を受けました(JICA統計2023)。この数値は1980年代の年間約2,000人程度から大幅に増加しており、日本国内における外国人材の存在感を高めています。
技能実習制度との関与
技能実習制度は法務省・厚労省・入管庁が主管ですが、JICAも「途上国への技能移転」の理念に共鳴し、調査や研修を通じて影響を与えてきました。ただし現場では「安価な労働力」として利用されることも多く、理念と実態の乖離が課題とされています。
特定技能や人材育成支援の取り組み
2019年に導入された特定技能制度でも、JICAは外国人材の研修や受け入れサポート事業に関与しています。とくにアジア諸国との人材交流プロジェクトは、日本国内の労働力不足対策と直結しており、今後ますます存在感を増す分野です。関連資料は 法務省 出入国在留管理庁 特定技能制度 2024 を参照できます。






関連記事:日本、バングラデシュ人材を5年で10万人受け入れ 制度と社会的影響を検証
JICAの活動が日本社会へ与える影響
自治体との連携事例
JICAは浜松市や川口市など、外国人住民が多い地域と協力し、多文化共生プログラムを展開しています。言語教育や地域交流イベントを支援することで、住民同士の理解促進を図っています。自治体レベルでの取り組みは、国の移民政策とも連動しやすい特徴があります。
多文化共生支援と住民生活への影響
外国人材受け入れに伴い、教育、医療、福祉などの現場で新たな課題が生じています。JICAが支援するプログラムは一部で効果を上げていますが、同時に地域住民の負担感や制度の持続性に関する懸念も存在します。
企業や就労市場への波及
JICAが後押しする人材交流は、日本企業にとっては新しい労働力確保の手段ですが、低賃金労働や雇用調整への影響も指摘されています。経済界は期待を寄せる一方で、国民生活への波及を慎重に見極める必要があります。






関連記事:首脳会談で日印人材交流を拡大 インド人 50万人 受け入れと新計画合意へ 国民生活への影響も
賛否・中立の三点整理(JICAをめぐって)
賛成意見
JICAは、外国人材受け入れ支援を通じて開発途上国と日本双方の成長を促す役割を担っており、人的ネットワークを活用した地域活性化や技能移転などに貢献しています(JICA公式 2023)。また、特定技能制度への支援や受入環境の整備を進めており、国際協力の側面と国内課題への対応を両立させた取り組みとして評価されています。
中立・調整的立場
外国人労働者受け入れにより日本の中小企業を支援する一方で、社会保障や法整備の遅れによる負担増や違法就労への懸念など、制度の実効性と社会的整合性をどのように担保するかという課題も存在しています(East Asia Forum 2019)
反対意見
JICAのアフリカ・都市連携構想は、「移民政策」と誤解され、市や住民が強い反発を示す事態を招きました。「移民を招き入れるのか」といった混乱を生み、排外的な反応を誘発した例は制度の受容性に重大な懸念を伴います(The Guardian 2025年8月27)。また、西洋や湾岸モデルのように外国人を一時的機能人材と位置づける制度運用には、文化的均質性への不信感が根強いとの分析もあります(Le Monde 2024年6月26日)






FAQ:よくある疑問
Q:JICAは何をする組織ですか?
A:外務省所管の独立行政法人で、日本の政府開発援助(ODA)を実行する中核機関です。技術協力・有償資金協力・無償資金協力を柱に、途上国の発展と国際社会の安定に寄与します(JICA 組織概要 2025)。
Q:JICAは日本国内とも関係があるの?
A:あります。海外人材の研修受け入れ、多文化共生プログラム、自治体連携などを通じて、日本の教育・医療・企業人材にも波及します(JICA 年次報告書 2024)。
Q:技能実習や特定技能とJICAの関係は?
A:技能実習・特定技能は所管が法務省・厚労省・入管庁ですが、JICAは人材育成・研修や受入支援の知見を持ち、連携・支援領域があります。現場では「労働力確保の機能が強い」との指摘もあり、理念と実装の整合が論点です。
Q:JICAの規模感は?
A:2024年度のJICA関連予算は約1.2兆円規模(ODA関連計上含む)、職員は国内外で約1,900人です(外務省 ODA関連資料 2024/JICA 年次報告書 2024)。
Q:日本社会へのメリットと課題は?
A:国際協力の成果や人材ネットワークが国内産業や地域活性化に資する一方、受入現場の教育・医療・生活支援の整備が追いつかないと摩擦が生じ得ます。透明性の高い制度運用と地域合意形成が鍵です。
まとめ


















今後の見通し
JICAは国際協力を担う機関であると同時に、日本国内での外国人材受け入れや多文化共生に影響を与える存在です。自治体や企業への波及は今後さらに広がるとみられ、制度の持続性と国民生活への影響を注視する必要があります。
JICA関連記事
関連記事①:JICAとは 活動を解説 国際協力と日本社会への影響
関連記事②:JICAと技能実習・特定技能制度 役割と日本社会への影響を解説
シリーズ次回は「技能実習制度とJICAの関与」を取り上げ、制度の理念と現場の実態を分析します。

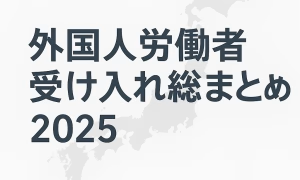
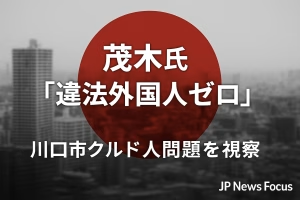
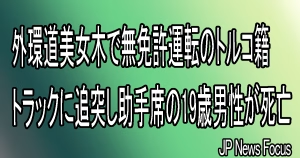
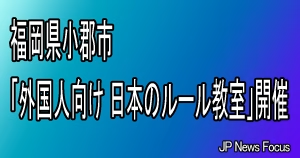
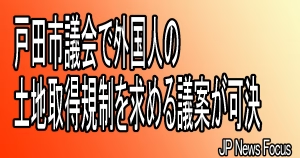
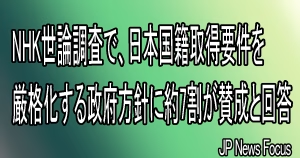
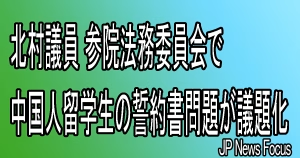
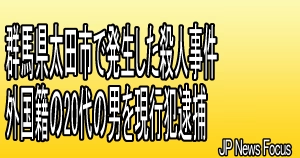
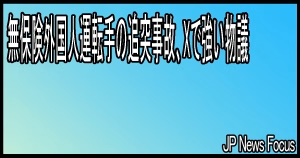
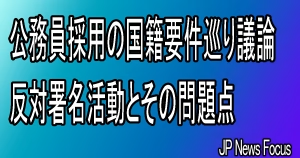
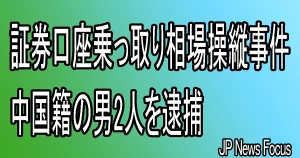
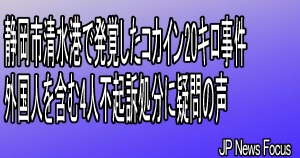

コメント