公開日:2025年8月30日 最終更新日:2025年9月8日
東京都板橋区では、外国籍児童がこの10年で倍増し、教育現場に大きな負担を与えています。区の予算は12億円から19億円へと大幅に増額される予定ですが、支援員不足や家庭環境の壁は依然として解消されていません。欧州の事例と比較すると、日本の対応は遅れており、今後の制度設計が問われています。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ


下村元文科相の発言に注目
下村博文元文部科学相は自身のYouTubeチャンネルで板橋区の小学校における外国籍児童の急増について言及しました。
▶ 下村博文元文科相YouTube動画(板橋区小学校の事例)
動画によれば、外国籍児童は10年前の約500人から現在は約1,000人規模に達し、一学年あたり数十人単位で入学するケースも増えています。






板橋区の現状:一学年で数十人規模に
同動画によると一学年に1人や2人程度だった外国籍児童が、現在では数十人単位で在籍するようになったそうです。言語面の壁に加え、特別な支援を必要とする児童も一定数おり、担任や支援員の負担は複合的に増大しています。(他、参考資料:学校就学率データRESA S)






全国的にも増える外国籍児童
文部科学省の2023年度調査によると、日本語指導が必要な児童生徒は全国で69,123人。10年前に比べ約1.9倍に増加しています(文部科学省2024)。
特に中国語やポルトガル語を母語とする児童が多く、地域的な偏在が課題となっています。






板橋区は外国籍児童の急増を受け、教育予算を12億円から19億円に増額予定です。重点施策は以下の通りです。(板橋区令和7年度(2025年度)教育費当初予算概要)
・日本語指導教員の拡充
・専門スタッフの増員
・外国籍児童が多い学校への重点配置
・特別支援を必要とする児童への追加支援






内部リンク:入管庁が不法残留者の増加を公表 埼玉・愛知・東京に集中
ことば支援員が直面する課題
ことば支援員からは「家庭で日本語を使わないため習得が進まない」「学習意欲が低い」といった悩みが挙げられています。親子ともに日本語を覚えようとしない例や、中国語コミュニティに依存する家庭環境が指摘されています。






外国人児童への対応と新たな構想
支援員不足が深刻な中で、板橋区や文科省は「プレスクール構想」を検討しています。これは入学前に日本語を集中的に学び、基礎を身につけてから小中学校に進学する仕組みです。(文部科学省総合教育政策局国際教育課2024、学校準備プログラムの導入例(別地域))






海外事例との比較:欧州の対応
ドイツでは入学前に言語テストを義務化し、不足する児童は補習を受けます。フランスでは「UPE2A」と呼ばれる特別学級でフランス語教育を受け、段階的に通常学級へ統合されます。
日本は自治体任せで、全国標準が未整備です。今後は「入学前教育の制度化」や「多言語支援員の常勤化」が課題です。






制度をめぐる視点


















FAQ:よくある疑問
Q:なぜ板橋区で外国籍児童が急増しているのですか?
A:技能実習生や留学生の家族、在留外国人の定住化が進み、都市部を中心に児童数が増えているためです。板橋区は交通の便や住宅事情から外国人世帯が集中しやすい地域とされています。
Q:学校現場で一番の課題は何ですか?
A:日本語を理解できない児童が多く入学することで授業運営が難しくなる点です。支援員不足や教員の負担増により、日本人児童の学習環境にも影響が及ぶことが懸念されています。
Q:日本の対応は海外と比べてどうなのですか?
A:ドイツやフランスでは入学前教育や特別学級が制度化されていますが、日本は自治体任せで全国標準が未整備です。そのため地域によって支援体制に差があり、制度設計の遅れが課題となっています。
国益的示唆と今後の展望
外国籍児童の教育は日本社会の将来を左右します。支援不足が続けば孤立や治安悪化につながりかねませんが、早期から日本語教育を行えば将来的な人材資源になり得ます。国全体での制度設計が遅れれば教育格差が固定化する可能性があるので、国レベルでの制度整備と地域格差の是正が急務です。








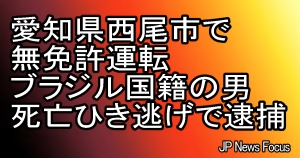

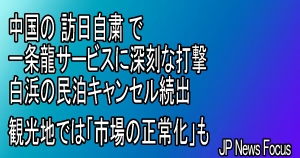
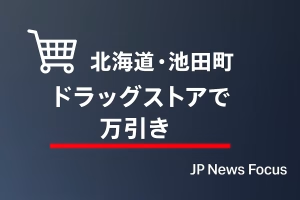
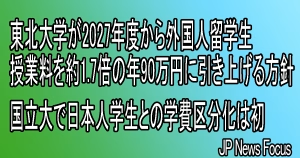
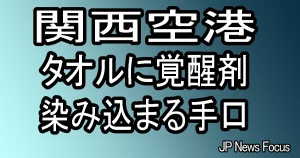
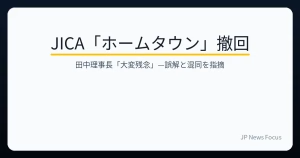
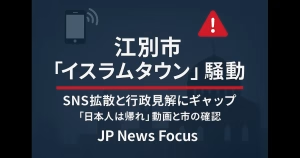
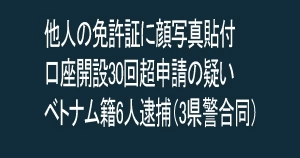
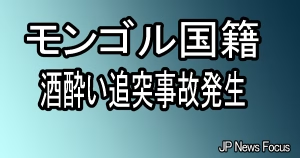
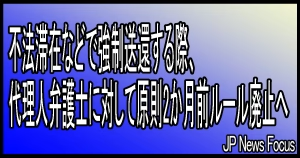
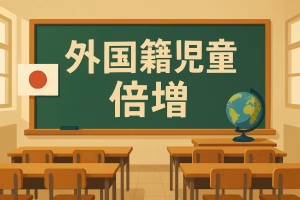
コメント