公開日:2025年9月10日 最終更新日:2025年9月10日
今何が起きている?
2025年8月末から9月にかけて、法務省入管庁は日本における外国人の中長期受け入れ方針の見直しに着手しました。検討対象には「受け入れ人数の総量規制」も含まれ、賃金水準や治安、社会保障への影響を調査する方針です(産経新聞 2025年9月10日)。技能実習制度はすでに廃止が決まっており、新たな「育成就労制度」への移行が進められています。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ








背景とこれまでの経緯
外国人受け入れ制度の柱であった技能実習は、2023年の有識者会議による最終報告書(厚生労働省)を経て、2024年6月に関連法が改正・成立しました。施行は公布から3年以内とされ、2027年までに「育成就労制度」へ移行することが決まっています。有識者会議は16回開催され、現行制度の問題点(人権侵害・転籍制限・低賃金)を整理したうえで、新制度の方向性を提示しました。
出典:出入国在留管理庁「令和6年6月末現在における在留外国人数について」
海外の事例から見る人数規制
海外ではすでに「人数や質のコントロール」が常識となっています。英国(GOV.UK)は技能労働ビザに高い賃金基準(年収3.8万ポンド超)を設定し、受け入れを高技能に限定しています。オーストラリア(Immigration and citizenship)は毎年「プラニング・レベル」を定め、分野別に人数を調整。カナダ(National Post)も2024年から留学生数の上限導入を発表しました。これらは単なる人数削減ではなく、社会コストの管理と質の担保を狙った施策です。
地域・社会への影響
日本でも人数規制が導入されれば、労働市場や地域社会への影響は避けられません。人手不足の現場では供給減少による混乱が懸念される一方、受け入れ数の無制限拡大は賃金低下や治安不安、社会保障負担を増幅させるリスクがあります。特に住宅や教育インフラを抱える自治体にとっては「どこまで受け入れられるか」が切実な課題となります。












関連記事:下村博文元文部科学相 東京都板橋区の小学校における外国籍児童の急増について言及
賛否・中立の三点整理


















まとめ/今後の見通し
入管庁が進める受け入れ方針の見直しは、人口減少と人手不足が進む日本社会にとって避けられない課題です。海外のように「質重視・人数規制」の手法を参考にしつつ、国内の労働市場や自治体の受け入れ能力を踏まえた柔軟設計が求められます。今後は賃金・治安・社会保障への影響データを公開し、国民に説明責任を果たしながら制度の持続性を高めることが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q:外国人の受け入れ人数は今後減るのですか?
A:現時点では「必ず減らす」とは決まっていません。入管庁は人数上限を含めて調査・検討を始めた段階であり、賃金や治安、社会保障への影響を分析したうえで具体案をまとめる方針です。
Q:技能実習制度はどうなるのでしょうか?
A:技能実習制度は2024年6月に廃止が決定し、2027年までに「育成就労制度」へ全面移行する予定です。転籍制限の緩和や賃金確保などが盛り込まれる見込みです。
Q:海外では人数規制は当たり前なのですか?
A:はい。英国は賃金基準を高く設定し高技能人材に限定、オーストラリアは毎年の受け入れ上限を設定、カナダは留学生数を制限するなど、人数や質を調整する施策が一般的です。
Q:日本が人数規制を導入すると地域社会にはどう影響しますか?
A:人手不足の現場では混乱が懸念されますが、無制限に拡大すると賃金低下や社会保障負担増につながります。どの分野でどれだけ受け入れるか、バランス設計が重要です。
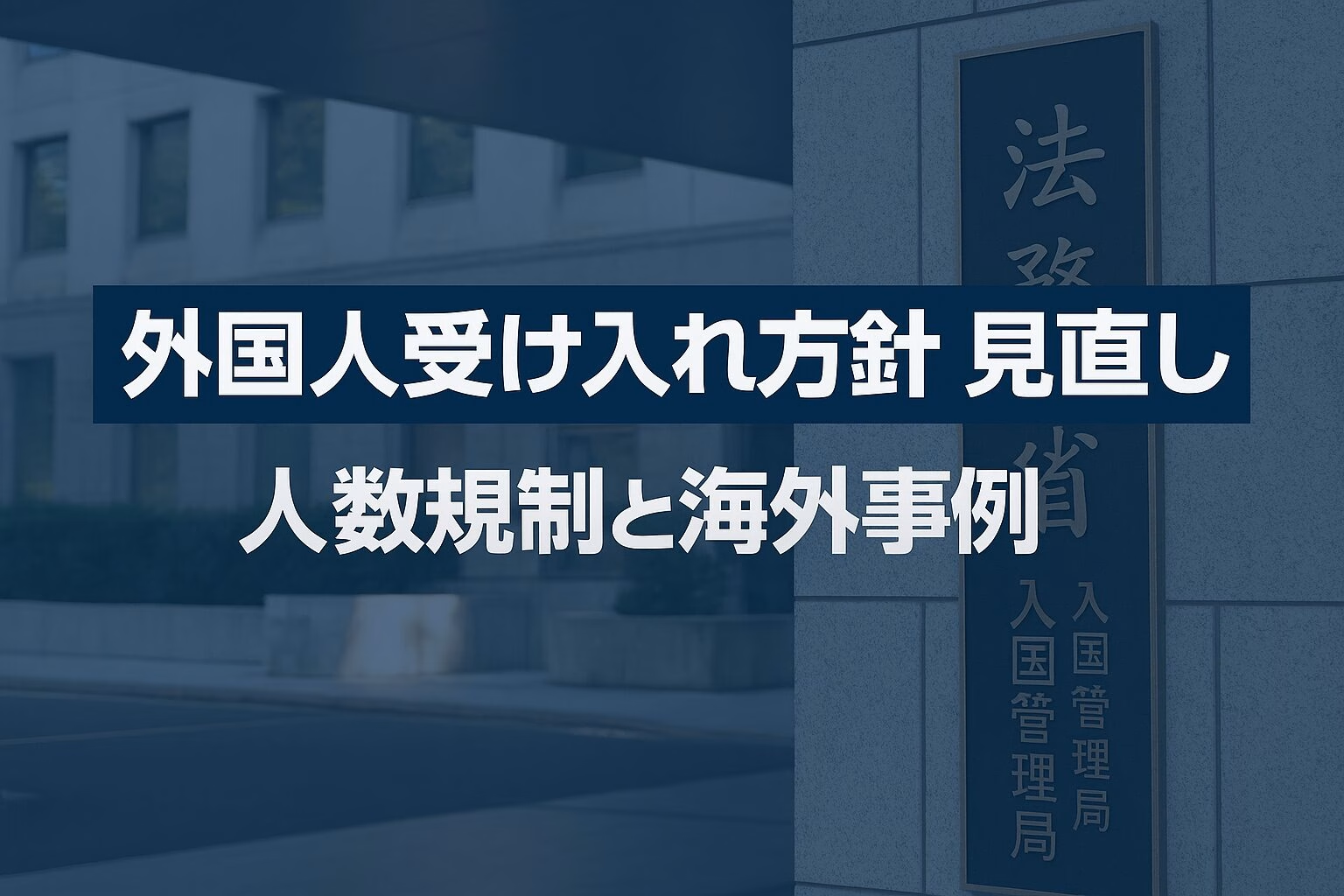
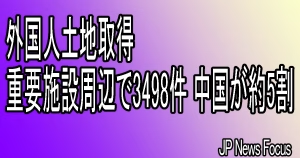

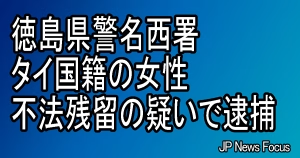
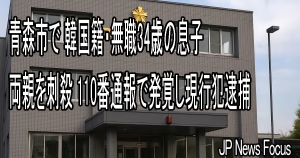
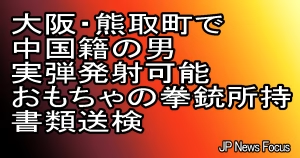
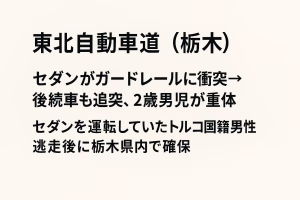
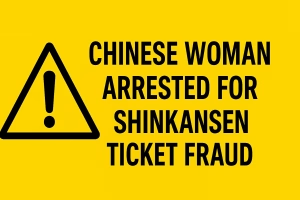
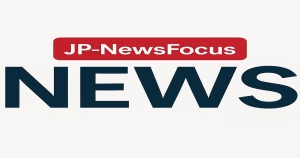
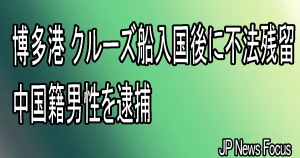
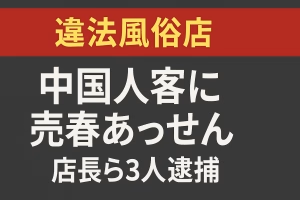
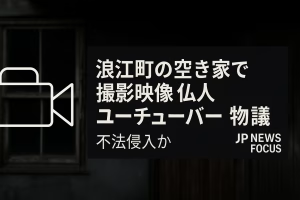
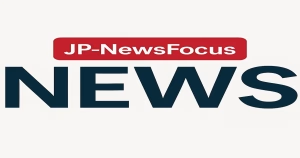
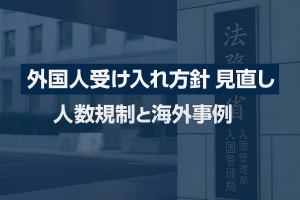
コメント