公開日:2025年9月18日
最終更新日:2025年9月18日
人口減少と人手不足を背景に、外国人技能実習制度を利用した勧誘が企業に届き始めている。ある企業に送られてきたFAXには「カンボジア人技能実習生の採用はいかがですか」との宣伝文句が並び、住所や連絡先も記載されていた。しかし実際に住所を確認すると更地であり、実態の不明な業者である可能性が高いことがわかった。制度移行期に便乗するこうした動きは、受け入れ企業にとって大きなリスクとなり得る。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ


勧誘FAXの内容
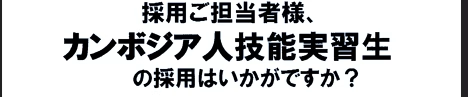
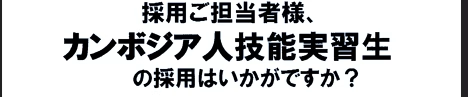
問題のFAXには、次のような文言が並んでいた。
- 「カンボジア人技能実習生の採用はいかがですか?」
- 採用面接は土日・夜間にも対応、オンライン面接も可能
- メリットとして「低コスト」「安定した長期雇用」「勤勉な若者」を強調
- 発信元として会社名・住所・担当者名が記載
一見すると制度を利用した通常の案内のようにも見えるが、調査を進めると違和感が浮かび上がった。
実態調査で判明したこと
FAXに記載された住所(茨城県下妻市)を実際に確認したところ、そこは更地であった。隣接する建物は畳屋であり、記載された会社の建物は存在しなかった。
さらに「株式会社」を名乗っていたが、日本の法人登記簿には該当する名称が確認できなかった。カンボジア本社の存在は確認できるものの、日本支社や国内窓口としての実態は不透明である。
こうした事例は、制度の不透明さに乗じて「実態不明業者」が営業を行っている可能性を示している。
技能実習制度と人材受け入れの現状
外国人技能実習制度は1993年に導入され、日本の産業基盤を支える一方で多くの課題も抱えている。
法務省の統計によれば、2025年6月末時点で技能実習生は約358万8,956人が在留しており(法務省 令和6年末現在における在留外国人数について)、外国人労働者全体の中でも大きな比率を占める。
また厚生労働省によると、外国人労働者全体は2025年6月末時点で約230万2,587人に達している(厚労省 外国人雇用状況 2025)。その中でカンボジアやバングラデシュといった新たな国からの受け入れが増加し、制度の隙を突く業者の介在余地も広がっている。
制度改革と過渡期のリスク
技能実習制度は2027年に廃止され、新制度「育成就労制度」へ移行する予定だ(法務省 育成就労制度)。新制度では「人材育成」と「労働力確保」の二つの目的が明確化され、在留資格の移行も容易になるとされている。
しかし、制度改革の過渡期には監督体制が緩みやすく、今回のように実態の不明な業者が現れるリスクがある。






社会的な懸念とリスク
- 企業側のリスク
- 実態不明業者と契約すると、不法就労や人権侵害に巻き込まれる可能性。
- 万一問題が発覚した場合、受け入れ企業自身も責任を問われる。
- 制度への信頼性低下
- 虚偽住所や無登記法人による勧誘が横行すれば、制度全体への信頼を損なう。
- 真面目に運営している送り出し機関・監理団体の努力がかき消される危険。
- 地域社会への影響
- 実態の不明なルートで来日した労働者が定住化すれば、生活支援や地域共生の負担が増す。
クロ助&ナルカの掛け合いで整理する 賛否・中立の論点


















編集デスクまとめ/今後の見通し
今回のFAX勧誘は、技能実習制度をめぐる不透明な現実の一端を示すものだ。制度の移行期に便乗する形で、実態の不明な業者が企業へ接触していることは、人材受け入れのリスクを浮き彫りにする。
今後の「育成就労制度」への移行では、監督体制や情報公開の強化が不可欠だ。企業にとっても「どのルートから人材を受け入れるか」を見極めることが、将来のリスク回避に直結する。
国益を守る視点からすれば、「いかに受け入れるか」の透明性と監督強化こそが問われている。

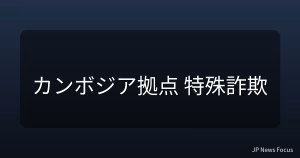
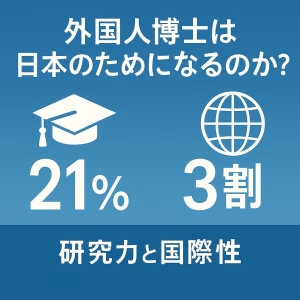
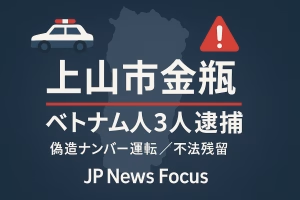

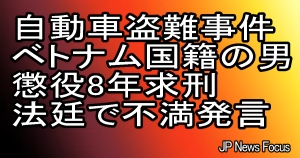
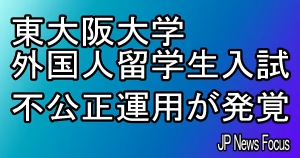
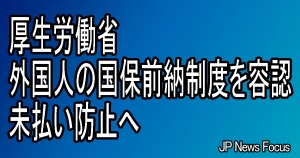
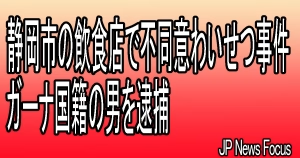

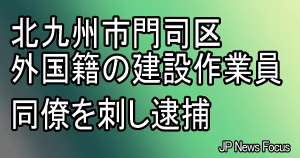
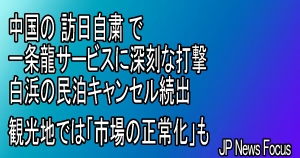
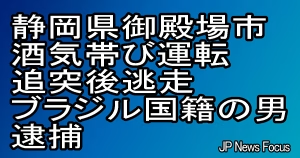

コメント