火葬が当たり前とされてきた日本で、近年「土葬墓地」が増加しています。背景には外国人の増加による宗教的ニーズがあり、さらに一部の日本人も希望するようになっています。一方で、宮城県では整備計画が撤回されるなど、地域社会で摩擦も。葬送の多様化は“必然”なのか、それとも社会的負担を拡大するのか――。
 編集長クロ助
編集長クロ助日本で土葬が希望者が増えるにゃ。



でも外国人が増えている以上、避けられない変化かもしれませんね
出典:ライブドアニュース(2025年9月)
関連記事:宮城県知事が土葬墓地整備について イスラム教徒配慮から一転 白紙撤回 知事発言から白紙撤回までの時系列まとめ
日本の葬送制度 ― 火葬が主流
厚労省(2022年)によると、日本の火葬率は99.97%と世界最高水準です。土葬は禁止されてはいませんが、多くの自治体が条例や墓地規則で制限しており、一般的にはほとんど選択肢に入りません。
土葬墓地の増加データ
ライブドアニュース(2025年9月22日)によれば、土葬墓地は7年で5倍に増加しています。埼玉県本庄市の「本庄児玉聖地霊園」では6年前から土葬を受け入れ、1区画30万円で提供。全国では十数か所に拡大している状況です。
外国人増加と宗教的背景
イスラム教徒やキリスト教の一部宗派では土葬が必須とされます。在日ムスリム人口は約20万人規模(早稲田大学調査 2021年)とされ、労働力受け入れや留学生の増加に伴い、宗教的理由からの土葬需要が拡大しています。
土葬の現状
- 火葬によらない埋葬(=土葬)は全国で2,180件。
火葬場の老朽化と更新課題
- 施設の67%が2000年以前の建設。
- 新設・改築を検討しているのは22.9%。主な理由は老朽化。
衛生・安全管理の課題
- 感染症チェックを「常に実施」52%。
- コロナ関連のみ対応が23%。
- 粉じん対策は不十分な施設も多い。
遺体安置と残骨灰処理
- 安置設備があるのは40%。収容力は平均2体と少ない。
- 残骨灰処理は業者委託が76%。有価物(金属など)売却も一部あり、透明性課題。



安置スペースが少なくて、処理の透明性にも課題があるにゃ



葬送の多様化に対応するには、設備や説明の整備も欠かせませんね
日本人希望者の増加
「自然に還りたい」「火葬より費用が安い」などの理由から、日本人の一部でも土葬を望む人が出ています。都市部では墓地不足もあり、地方の霊園に注目する動きも見られます。
宮城県での整備撤回
宮城県は土葬墓地整備を検討しましたが、地域住民の反発や衛生面の懸念を理由に撤回しました。地元からは「地下水汚染の恐れ」「治安不安」といった声が上がっていました。
専門家の見解
宗教学者は「葬送の多様化による必然」と指摘します。少子高齢化と多文化共生の中で、今後は土葬受け入れも選択肢として社会に定着する可能性があるとの見方です。
関連記事:宮城県のイスラム土葬墓地検討 署名受取拒否が波紋呼ぶ
編集部クロ助とナルカの視点から



衛生面や地域への影響が心配だにゃ。住民の反発も当然かもしれないにゃ



でも宗教の自由は守る必要がありますよ。ムスリムの人にとっては生活に直結しますし



日本人まで希望者が出てきたのは意外だにゃ。社会の多様化を映しているんだにゃ



結局は地域とどう折り合いをつけるか、その仕組み作りが問われますね
編集デスクまとめ
土葬墓地の増加は、外国人問題だけでなく、日本人自身の価値観の変化も反映しています。しかし地域社会の受容には限界があり、制度・衛生面の調整は避けられません。
「多様化は必然」という見解に対し、日本社会がどう折り合いをつけるか。今後の自治体判断が焦点となります。
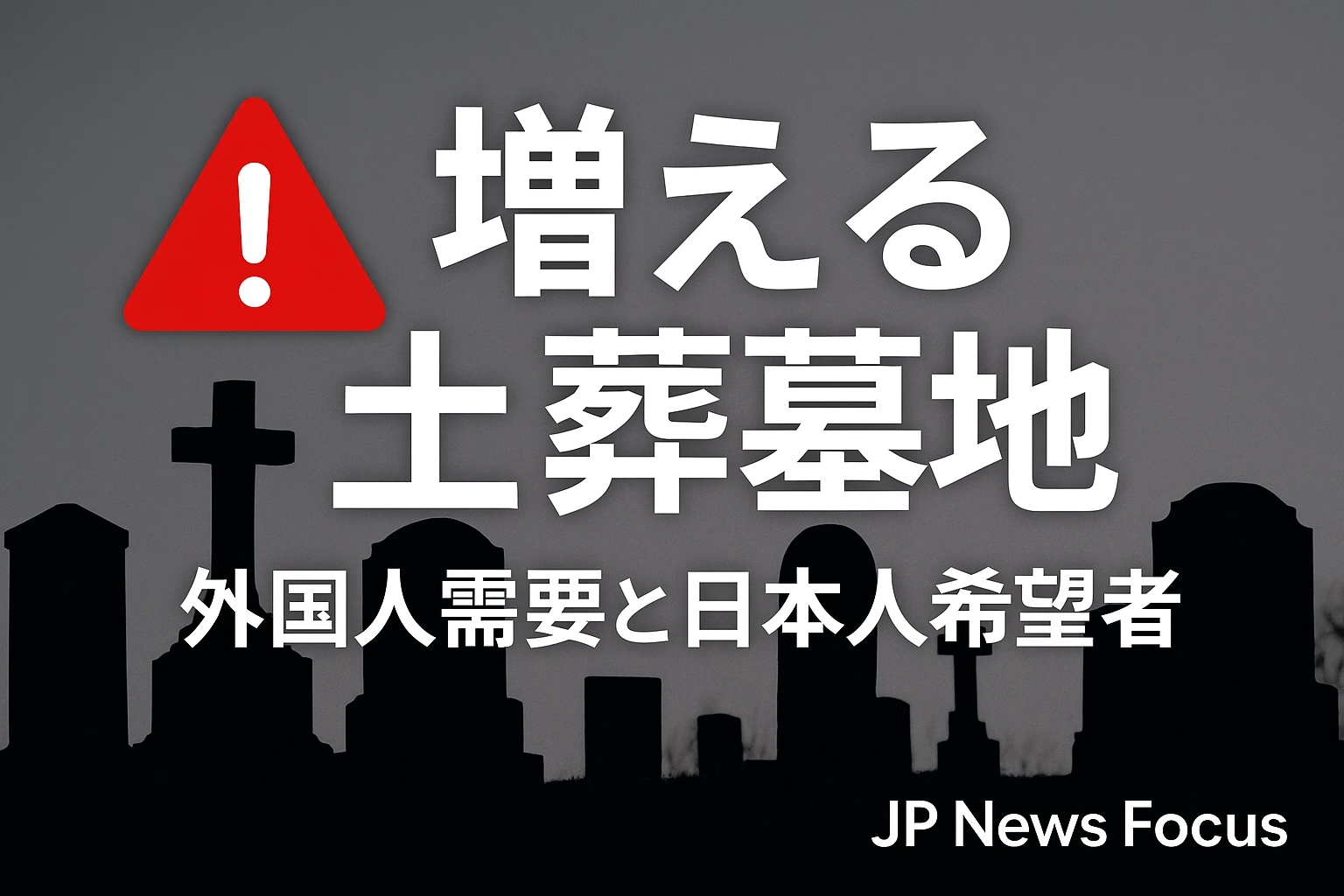
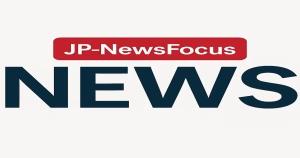
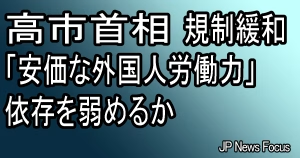

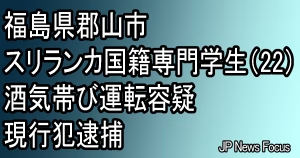
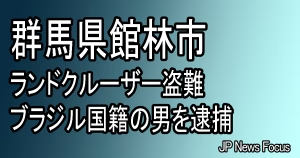
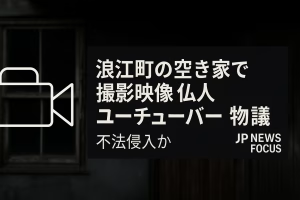

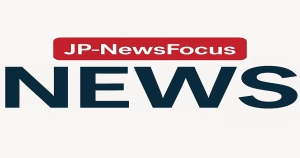
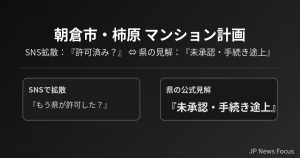
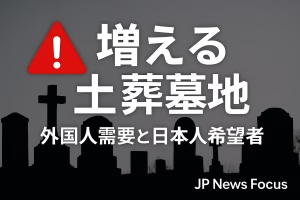
コメント