公開日:2025年8月30日 最終更新日:2025年9月9日
出入国在留管理庁統計(2025年7月公表)によれば、2025年6月末時点の不法残留者は82,012人で、前年同期比7.0%増となりました。摘発件数は12,458件(前年比+11.2%)で、近年の中でも高い水準です。背景には技能実習生の失踪や在留特例の終了があり、日本社会に波及しています。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ


摘発増加の背景
摘発増加の要因として、技能実習制度の構造的問題が挙げられます。2024年度だけで失踪者は約9,000人にのぼり、多くが期限切れ後も不法就労を続けていました(法務省 2024年統計)。
また、新型コロナ禍で一時的に認められていた在留期間の特例延長が終了し、入管庁による在留管理が厳格化。これにより摘発件数が増加したとみられます。






地域別に見た特徴
川口市の外国人比率は、令和6年(2024年)4月1日時点で人口607,279人中44,441人で、**7.32%**です。これは同市の住民基本台帳をもとにした公的データです。(川口市公式サイト)
また、2024年12月の統計によれば、外国人比率は**7.9%**に達し、1979年以降で最も高い水準です。(アセットマネジメントコンサルティング株式会社)
川口市が「全国1位の在留外国人数」であるとの報道もあり、地域コミュニティの特徴を理解する上で有用です。(優日堂)






不法残留者数の推移と国際比較
日本の不法残留者数は、1993年の約29万人をピークに減少し、2017年には約6万5千人にまで減りました。しかし近年は再び増加傾向にあり、2025年6月時点で約8万2千人に達しました(入管庁統計)。
国際的に見ると、韓国の不法滞在者は2024年時点で約42万人と推計されており、総人口比では日本を大きく上回ります。欧州でも不法滞在者は数十万人規模で存在し、移民政策の難しさは各国共通の課題です。






不法残留者が従事する産業と現場の声
不法残留者の多くは人手不足が深刻な業種で働いています。建設業や農業では「短期的に働き手を確保するために、在留資格切れの人材が頼りになっている」という現場の声もあります。介護分野でも、特定技能制度の枠に入らない外国人が非公式に雇われる例が報告されています。
一方で、事業者側は「不法就労者を雇えば摘発のリスクがあり、経営の信頼を損なう」と不安を抱えています。自治体からは「正規ルートでの就労を拡大しない限り、違法労働に依存せざるを得ない」という現実が指摘されています。
(参考資料:弁護士JP)






不法残留者をめぐる視点


















FAQ:よくある疑問
Q:なぜ不法残留者数は再び増えているのですか?
A:コロナ禍で一時的に在留期間の特例延長が認められていましたが、終了後に摘発が増えたこと、また技能実習生の失踪が続いていることが背景にあります。人手不足が深刻な分野で不法就労が温存されやすい点も影響しています。
Q:不法残留者は全体のどのくらいの割合ですか?
A:2025年6月末時点で約8万2千人で、在留外国人全体(約343万人)の2.3%前後にあたります。割合は小さいものの、特定の地域や産業に集中するため、影響は無視できません。
Q:地域ごとに不法残留者が多いのはなぜですか?
A:建設や製造など人手不足が集中する地域では、労働需要が高いため不法残留者も集まりやすくなります。川口市や愛知県などは外国人比率が高く、摘発件数も目立ちやすい傾向があります。
まとめと今後の課題
今回の入管庁統計は、不法残留問題の深刻さを改めて示しました。治安維持と公平性のために摘発強化は避けられませんが、同時に以下の制度改革が急務です。
・特定技能制度の柔軟化と拡充
・新制度「技能習得型雇用制度」への円滑移行
・透明性ある摘発手続きと国民への情報公開
・合法的就労ルートの明確化による人手不足対応
不法残留は単なる治安問題ではなく、日本の労働市場と社会の持続性に直結する課題です。国益を守る観点からも、取り締まりと制度改革の両輪が求められます。
また、国民的議論と透明なデータ公開が不可欠です。







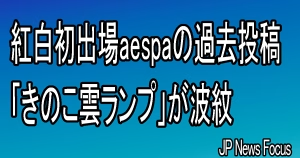
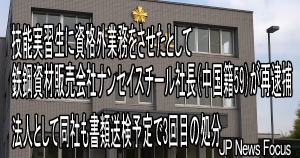

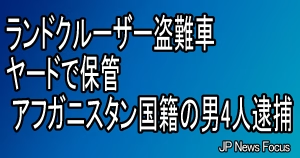
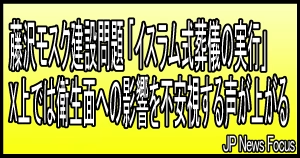
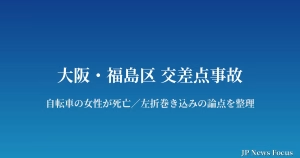
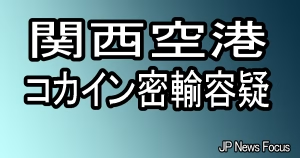
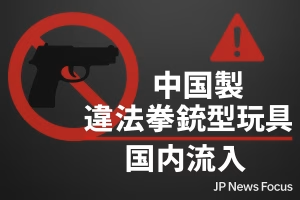
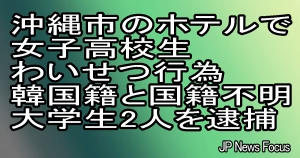
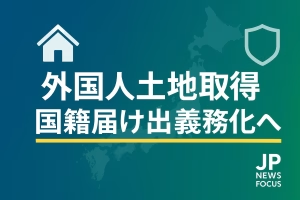
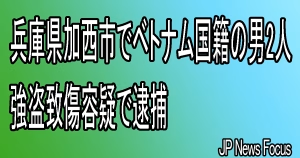
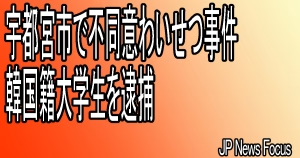

コメント