茨城県内の市長会と町村会が設けた「外国人との共生に関する特別委員会」は7日、外国人住民が増加する中で、自治体現場の課題を国に求める9分野の要望案をまとめた。年内に正式決定し、政府へ提出する方針だ。
目次
「外国人共生は国益」も 現場では課題山積
要望案では、外国人労働者や海外投資の存在を「我が国の産業と経済にとって必要不可欠」と評価する一方で、 行政窓口や教育現場で外国人との対応をめぐるトラブルが増えている現状を指摘。 委員会は「国が共生社会の明確なビジョンを示すべきだ」と訴えた。
特別委員会の神達岳志・常総市長は「外国人政策が基礎自治体任せになっており、窓口負担が増している」と述べ、 現場の人員・予算不足を背景に、国主導の体系的な方針策定を求めた。
要望の柱:9分野で制度改善を要請
委員会がまとめた要望の主な内容は以下の通り。
- 納税管理人の選任義務化 在留外国人に代わり税手続きを行う「納税管理人」の選任を義務づけ、未納や所在不明による徴税難を防ぐ。
- 交付金の柔軟運用 国が自治体に交付する「外国人受入環境整備交付金」の使途を拡大し、 生活相談や多言語対応などに弾力的に使えるよう制度を見直す。
- 不動産取得・利用の規制 在留資格に応じて外国人の土地・建物取得を制限できる法的仕組みを検討。 利用上のトラブル発生時に自治体が指導・是正できる権限を求める。
- 共生の理念と国民理解 「外国人受け入れ=国の成長戦略の一環」であることを明確にし、 国民の不安や誤解を解消するための広報・教育政策を求める。
現場の声:増える外国人、追いつかない制度
茨城県は製造業や農業を中心に外国人労働者が増加。 2024年末時点で県内在留外国人数はおよそ11万2000人(法務省統計)と過去最多を更新している。 特に常総市・筑西市・古河市では、外国人住民比率が10%を超える地区もあり、 ごみ分別や学校支援、福祉窓口での多言語対応など、行政現場の負担が増大している。
こうした実態を踏まえ、特別委員会は「外国人政策を国任せにせず、現場の声を反映させる仕組みが必要」と強調した。
クロ助とナルカの視点
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ外国人が増えると地域が変わるってよく聞くけど、現場の役所は大変なんだね。



にゃ。制度より早く現場が動いてるにゃ。 ルールや通訳体制が追いつかないと、住民と外国人の双方に不満が出るにゃ。



納税管理人を義務化って、かなり踏み込んだ提案じゃない?



そうにゃ。生活基盤が安定してる人は問題ないけど、短期滞在や転職移動が多い層では税の未回収が課題にゃ。
公平な負担を守る制度としては理にかなってるにゃ。
編集部でまとめ
- 事実確認:茨城県市長会・町村会の「外国人共生特別委員会」が9分野の要望案をまとめ、年内に国へ提出予定。
- 要点:納税・不動産・交付金・行政支援の4分野で制度改善を要求。「現場任せの外国人政策」からの脱却を促す。
- 国益的示唆:外国人の受け入れを前提とした共生政策には、秩序・財政・責任のバランス設計が不可欠。自治体の法的権限拡充が焦点となる。
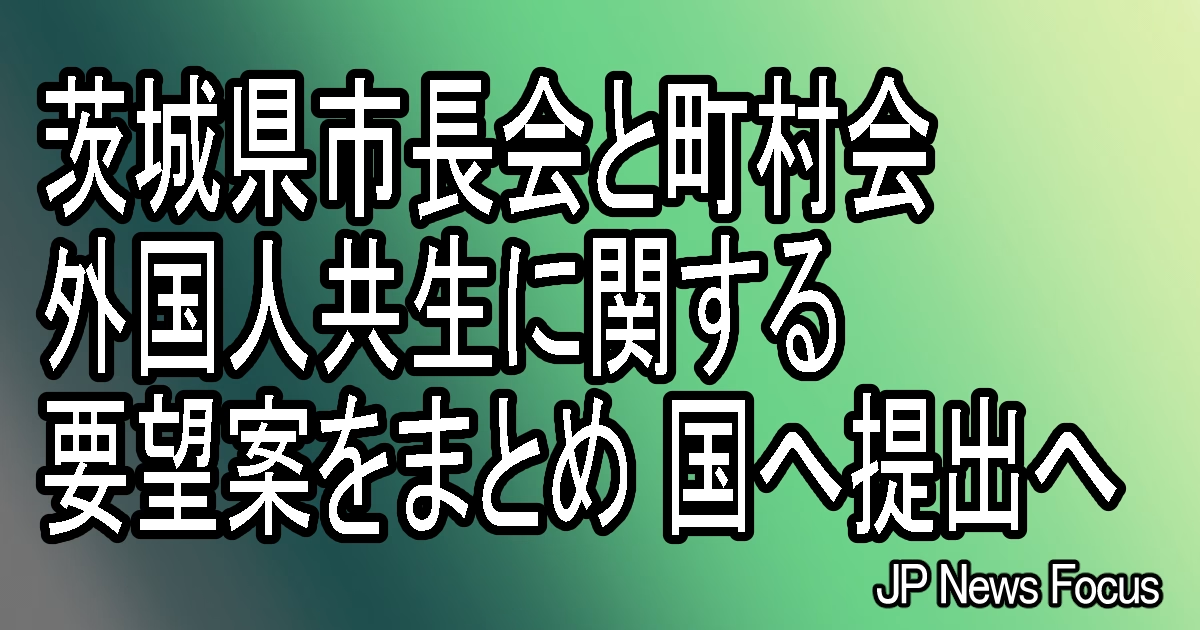
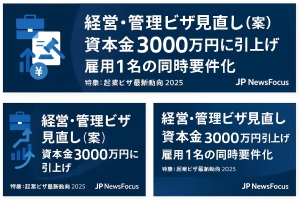
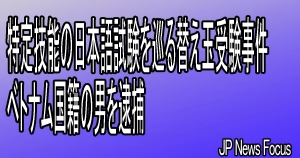
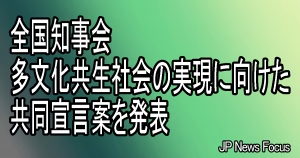


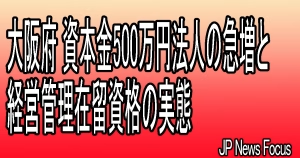
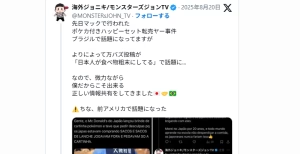

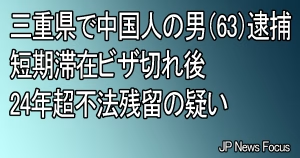
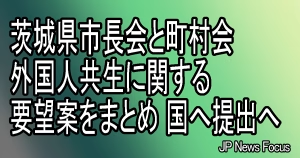
コメント