近ごろSNS上で「日本のスーパーに中国産米が並んでいる」という投稿が注目を集めている。実際に一部店舗では、中国産や混合米の表示が確認されており、消費者の関心が高まっている。報道・調査・農政関係者の分析をもとに、制度・経済・国益の三側面から整理する。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカえ、中国産のお米が普通にスーパーにあるの?



一部店舗では確認されているにゃ。ただし「偽装」ではなく「合法的輸入米」のケースもあるにゃ。背景には価格高騰と輸入制度の仕組みがあるにゃ。
目次
背景:SNSで拡散した“スーパーの中国産米”
今秋以降、SNS上で「店頭に中国産米があった」との投稿が複数拡散。実際に大手スーパー数店舗で、中国産もしくは混合米の表示が確認されている。読売新聞や週刊文春オンラインなども「輸入米流通の拡大」「産地偽装の疑念」を報じた。一方、中国の国営メディアも「日本市場で中国米が売られている」と自国の農業成長を強調するなど、日中双方で注目度が高まっている。
制度面:輸入米の仕組みと規制
- 日本では1995年のコメ自由化以降、SBS方式(売買同時入札)などを通じて一定量の輸入米が認められている。
- 中国産米も検疫・残留農薬検査などを経て輸入が可能。流通段階では「外国産」と明記する義務がある。
- 農林水産省は「輸入米は全体の消費量の1%前後であり、主に業務用・加工用」と説明している(2024年度統計)。
- ただし近年、国内価格の高止まりを背景に、スーパーが低価格帯商品の一環として輸入米を取り扱う例が散見される。
経済面:価格・供給の圧力
- 2024~25年産の国内コメ価格は高止まり。5kgあたりの小売平均は約2,800~3,000円。
- 一方、中国産やタイ産の輸入米は約1,500円台で販売され、価格差が2倍近い。
- 円安と物流コスト高により国産原料の価格が維持される中、流通業者が低価格商品を確保するため輸入米を選ぶ傾向も見られる。
- 中国側では「高品質化」や「輸出ブランド化」が進んでおり、東アジア諸国への輸出を拡大している(中国商務部統計2024年)。
安全・信頼性:表示と検査の透明性が焦点
中国産米だからといって即リスクというわけではない。日本の検疫基準を通過した米は安全性が確認されている。一方で、過去には「国産表示」で中国米を混入させた事例があり、消費者の不信感を高めた。 食品表示法では、単一原料米の場合は原産国を、複数原料米では使用割合の多い国を表記する義務がある。 ただし、加工・流通過程での「混米」「再袋詰め」には監視が追いつかないケースもあり、透明性確保が課題だ。
国益・農政的観点:自給率と制度の再設計
- 日本の食料自給率(カロリーベース)は2024年度時点で37%。うちコメの自給率は98%と高水準だが、輸入米が常態化すれば象徴的な「主食の国産維持」が揺らぐ懸念がある。
- 農業人口の高齢化と減反政策の転換期にあり、国内農家の収入維持が課題。輸入圧力が強まれば、地域の生産継続が難しくなる可能性も。
- 一方で、価格多様化を受け入れる柔軟性も必要。国産ブランド米と輸入低価格米の“すみ分け”をどう制度化するかが焦点。
- 消費者教育・産地トレーサビリティ・小売事業者の倫理的責任が今後の信頼回復の鍵を握る。
クロ助とナルカの視点



外国産のお米を食べるのは危ないの?



検査を通れば安全にゃ。問題は「どこ産か分からない状態」で売られることにゃ。消費者が選べる情報を整えることが大事にゃ。



国産のお米が減っちゃうのは困るね。



にゃ。農業を守るには「高品質・ブランド化」と「適正価格の維持」が欠かせないにゃ。安さだけで選ぶと、将来の食の安全が危うくなるにゃ。
編集部でまとめ
- 事実確認:スーパーで中国産米が確認された事例があるが、合法輸入・流通経路は制度上認められている。
- 課題整理:価格競争・表示の透明性・国内農家の採算維持をどう両立するか。
- 国益的示唆:自給率を支える国産農業と消費者選択の信頼性を確保する制度的整備が必要。
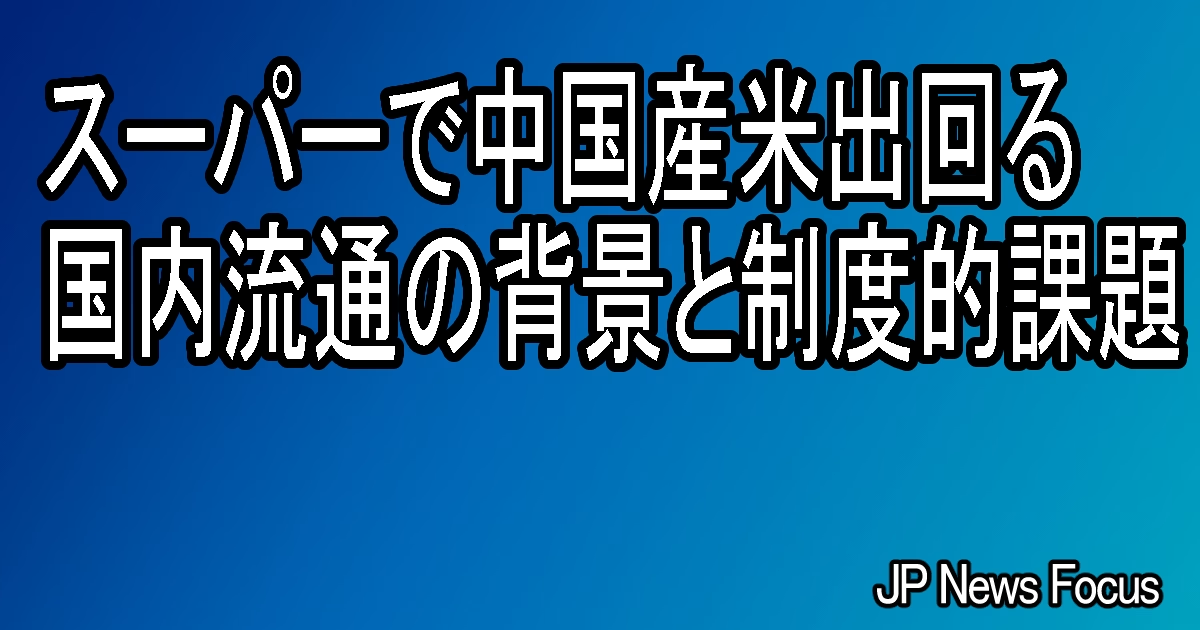
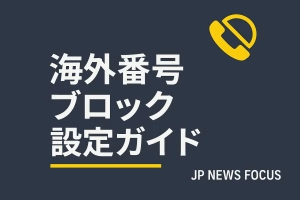
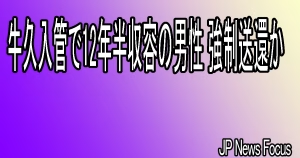

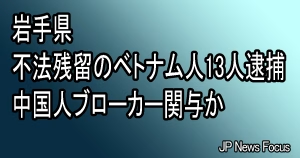
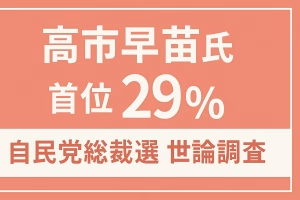
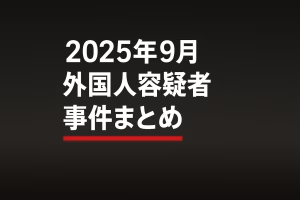

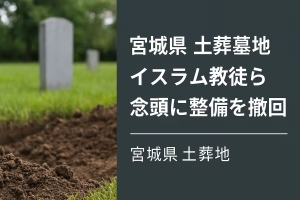
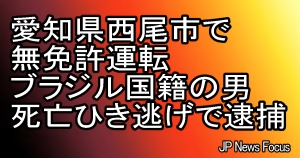
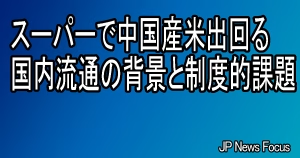
コメント