高市早苗首相が厚生労働相に対し、「労働時間の規制緩和」の検討を指示していたことが21日、関係者への取材で分かった。政府内で働き方改革の見直しを進める動きの一環で、残業上限や勤務間インターバル制度の柔軟化が議論の対象となる可能性がある。
 新人記者ナルカ
新人記者ナルカ労働時間の「規制緩和」って、働く側には厳しくならないの?



まだ検討段階にゃ。高市政権は「選択的な働き方の多様化」を掲げているけど、過労防止とのバランスが注目されるにゃ。
目次
概要
- 日時:2025年10月21日(22時16分報)
- 発表経路:関係者取材(共同通信報道)
- 内容:高市早苗首相が厚生労働相に「労働時間の規制緩和」を検討するよう指示
- 目的:働き方改革関連制度の再検討、労働生産性向上を視野
- 対象:残業上限・勤務間インターバル制度などの柔軟運用
関連背景
- 2019年施行の「働き方改革関連法」で、残業時間の上限規制・勤務間休息義務が導入。
- 近年は生成AI活用や副業解禁など、新しい就労形態への法対応が課題に。
- 経済界からは「業種・職種による柔軟化」要望が高まっていた。
クロ助とナルカの視点



企業側からの要望が強いの?



経団連などは「生産性向上と人材確保のため柔軟性が必要」と主張してるにゃ。けど労組側は「長時間労働が復活する」と警戒にゃ。
規制緩和が「安価な外国人労働力」依存を相対的に弱める理由
- 有効労働投入の拡張:残業上限や勤務間インターバルの柔軟化で、繁忙期に限った時限的な労働時間の再配置が可能になり、即時の人手不足を外国人採用で埋める必要性が相対的に低下。
- 自動化・省人化の採算改善:規制設計の見直しと並行して生産性KPIが重視されれば、ロボット・AI・省力機器の投資回収が早まり、「低賃金の補充」より「設備・IT置換」が選好されやすくなる。
- 総コストの見直し:言語教育・安全衛生の多言語対応、在留・雇用手続のコンプライアンス、定着支援などの間接コストが顕在化。国内人材の賃金引上げ+柔軟シフトの方が、総費用で優位になるケースが増える。
- 人材の質的転換:時短と長時間の二極化ではなく、繁閑対応・専門職化・兼業活用で「少数精鋭」を回す設計にシフト。量的補充(低賃金大量採用)の相対的メリットが縮小。
留意点(バランス)
- 健康・安全の下限は維持必須:規制緩和は過労の誘因になり得るため、勤務間休息の下限や健康確保措置、監督執行の強化を同時に設計する必要がある。
- 代替困難分野の現実:介護・農業・外食など、季節性や対人サービス性が高い業種では、国内人材と外国人材の「補完関係」が当面残る可能性がある。
- 賃上げと生産性:国内人材の賃金引上げ・訓練投資(OJT/短期訓練)とセットでなければ、質への転換は実を結びにくい。



ナルカ:規制緩和で外国人採用の“うま味”が減るってこと?



クロ助:相対的ににゃ。柔軟シフト+自動化+人材育成で国内の回し方が改善すれば、「安いから大量採用」の発想は持続性に欠ける、という整理にゃ。
編集部でまとめ
- 首相指示:厚労相に「労働時間の規制緩和」検討を要請。
- 狙い:労働制度の柔軟化による成長戦略支援。
- 今後:厚労省が有識者検討会を設け、制度改正案を年内に提示する見通し。
今後に必要なこと
- 短期は柔軟シフト、長期は自動化・技能高度化で「量→質」へ。外国人材は補完的人材として適正配置。
- 監督と健康確保の実効性が担保されない規制緩和は逆効果。下限規制+執行を強める設計が要件。
- 公共支援は「設備投資・再訓練・中核人材育成」を優先し、低賃金の外部依存モデルから脱却を促す。
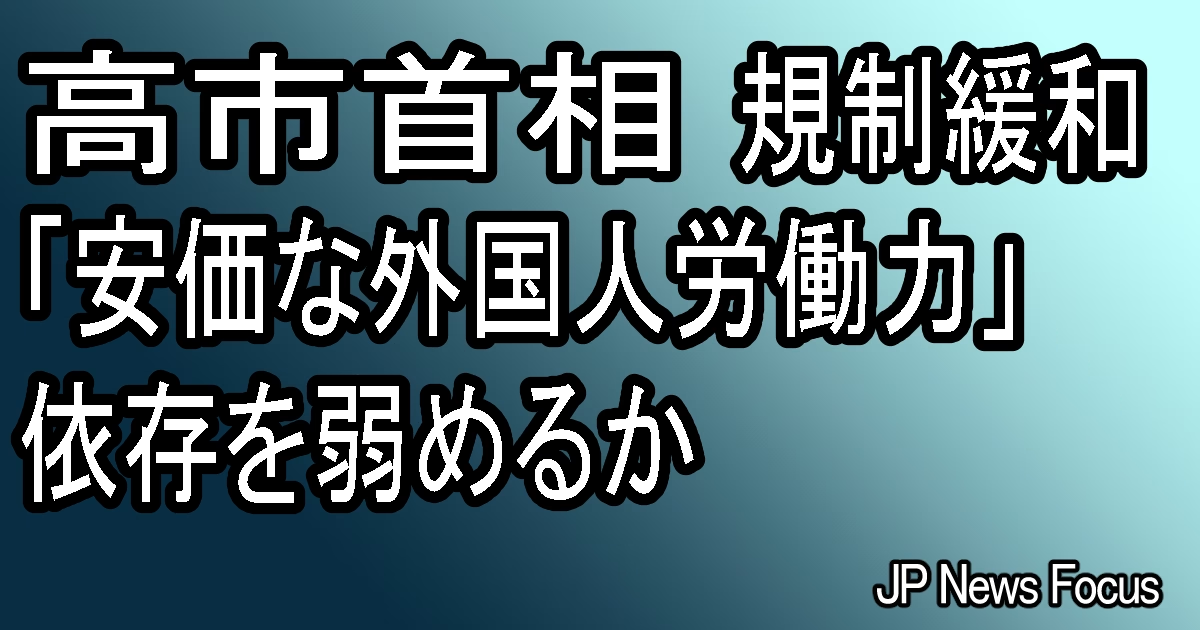
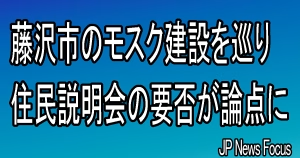
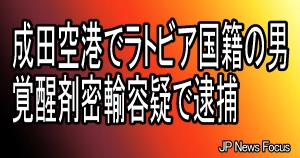
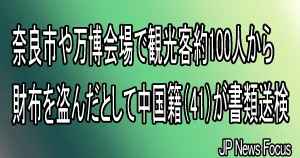
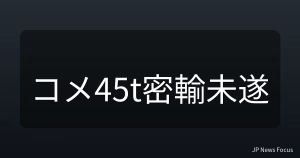
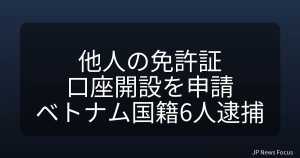


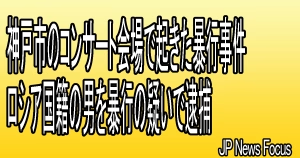
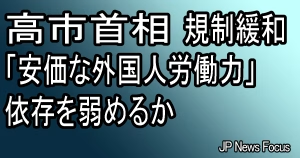
コメント